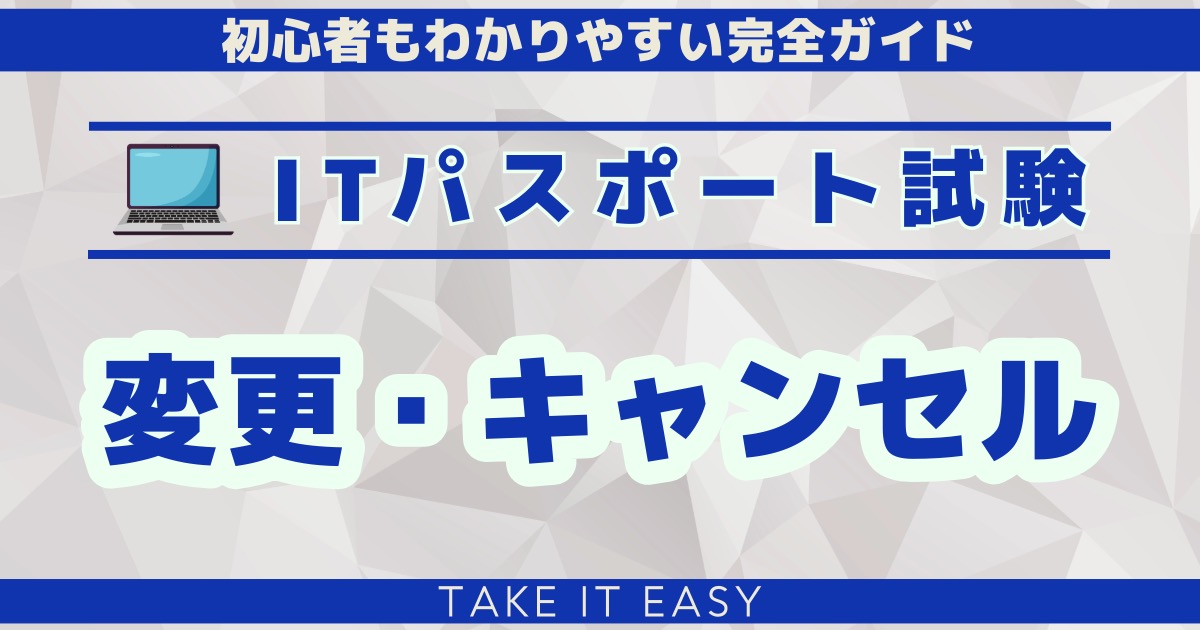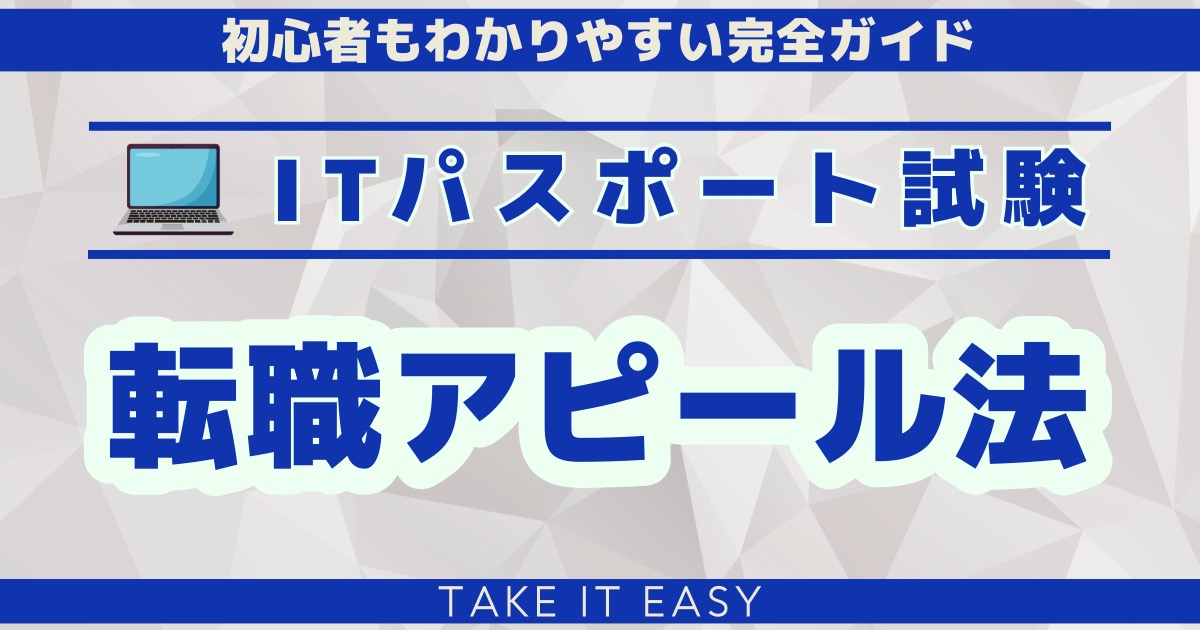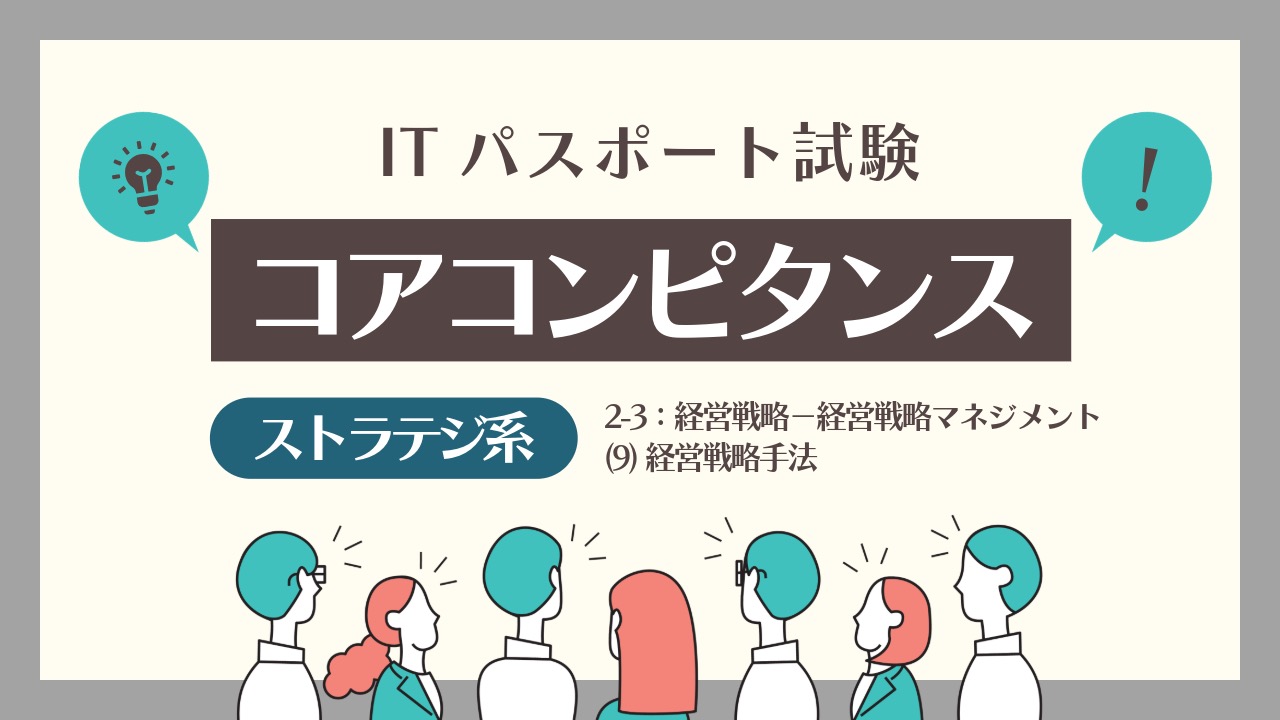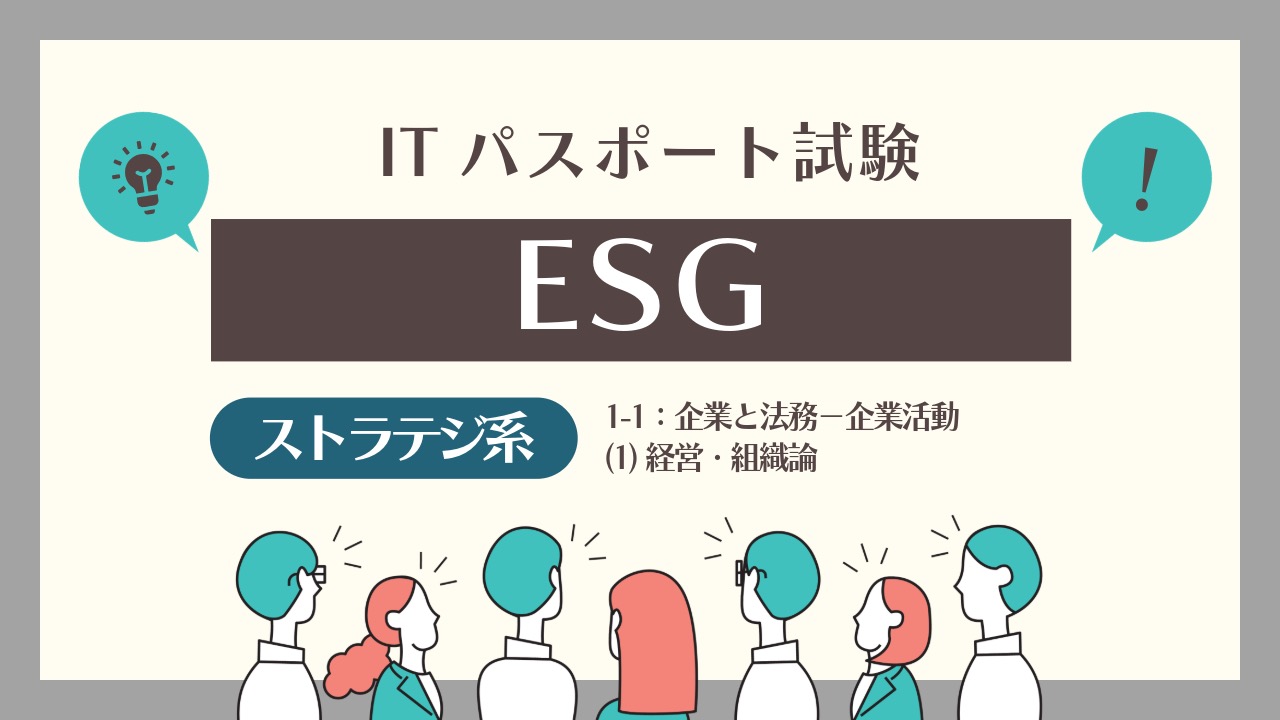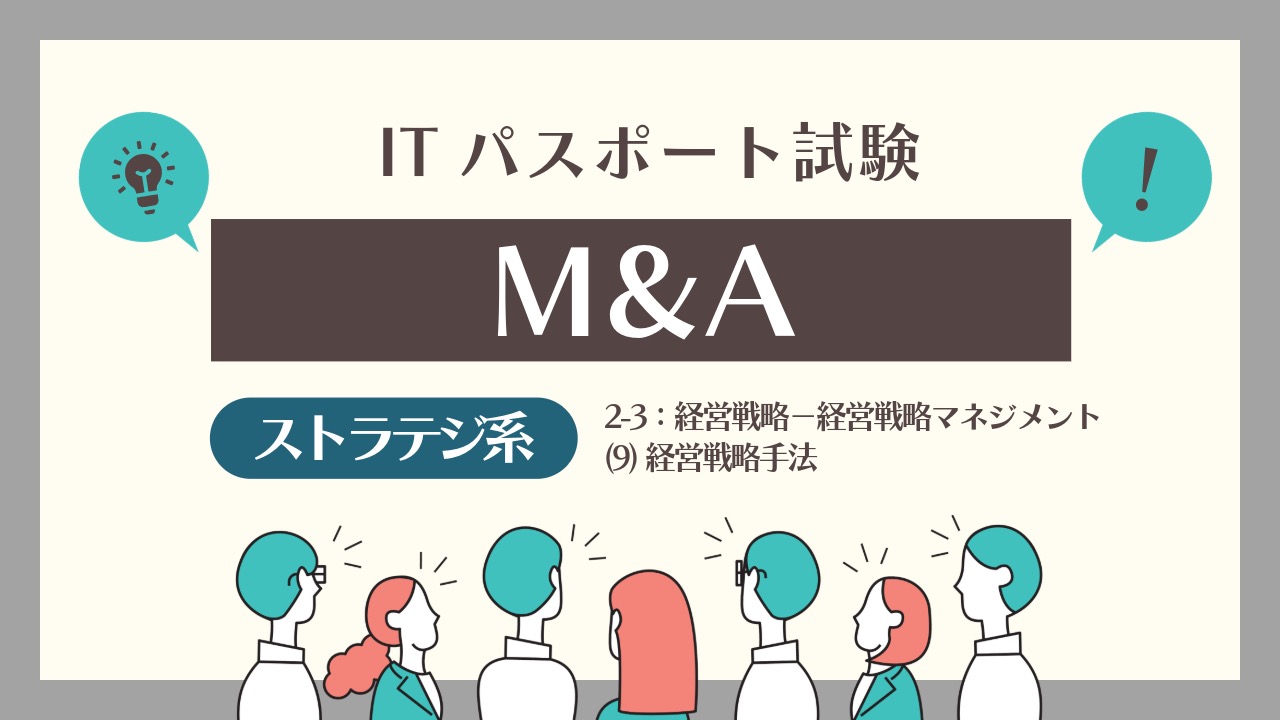CSV(共通価値の創造)とは?初心者でもわかるIT用語解説 | ITパスポート試験対策
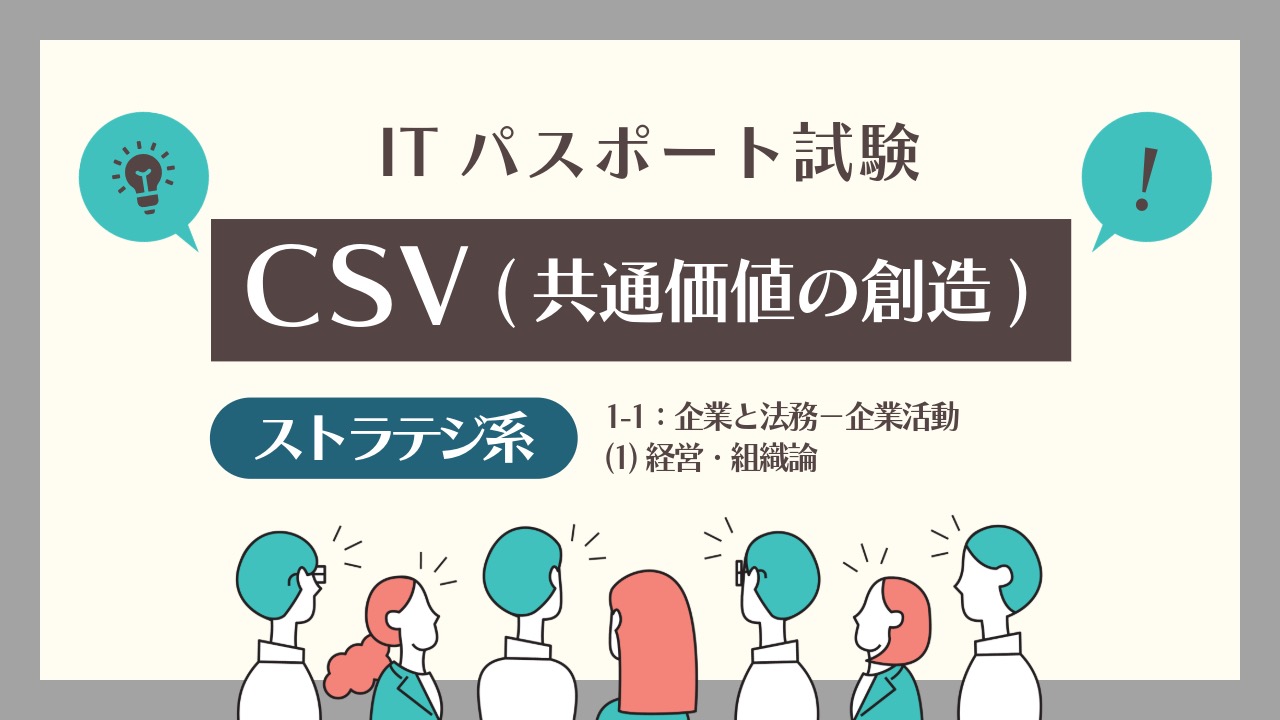
ITパスポート試験で経営戦略について学んでいると、「CSV」という言葉に出会うことがあります。この「CSV」は表計算ソフトで使うカンマ区切りのファイル形式ではなく、企業経営における重要な概念「Creating Shared Value(共通価値の創造)」を指します。
今日のビジネス環境では、企業の存在意義が問われる時代となり、単なる利益追求だけでなく社会への貢献も同時に求められています。
このCSVという考え方は、ITパスポート試験のストラテジ系分野(特に経営戦略)で出題されることがあるため、しっかり理解しておく必要があります。
この記事では、CSV(共通価値の創造)の基本概念から、なぜ企業が取り組むべきなのか、そしてITパスポート試験での出題ポイントまで、初心者の方にもわかりやすく解説していきます。
CSVの考え方を理解することで、現代のビジネス環境における企業の役割について深く考えるきっかけにもなるでしょう。一緒に学んでいきましょう!
CSVの基本概念と定義
CSVとは、「Creating Shared Value」の略で、日本語では「共通価値の創造」と訳されます。企業が競争力や経済性の向上を追求しつつ、同時に社会的な課題解決に取り組むための考え方です。
CSVの定義とは
CSVは、2011年にハーバード大学の経営学者マイケル・ポーター教授によってハーバードビジネスレビュー上で提唱された概念です。従来の企業活動では、「利益を上げること」と「社会に貢献すること」は別物として考えられがちでした。
しかし、CSVの考え方では、社会的な課題を解決することで企業の利益も同時に追求できると主張しています。つまり、社会的価値と経済的価値を両立させる経営手法なのです。
例えば、環境に配慮した製品を開発することで、社会課題(環境問題)の解決に貢献しながら、環境意識の高い消費者からの支持を得て売上を伸ばすというケースが考えられます。
CSVが生まれた背景
なぜCSVという考え方が生まれたのでしょうか?その背景には、従来の資本主義の限界があります。
従来の資本主義では、「企業は利益を追求し、社会的便益は後回しにする」「社会的便益はNPOやNGO・政府が行う」という考えが一般的でした。
しかし、こうした考えのもとでは、企業活動により水俣病などの公害問題や環境破壊、児童労働といった社会問題が発生してきました。
これらの問題に対処するため、政府は企業に多くの制約を課すようになり、結果として企業の利益創出が難しくなるという悪循環が生じていました。
そこで生まれたのが、社会課題の解決と企業利益の追求を両立させるCSVという考え方です。CSVによって、企業は自らの強みを活かして社会課題を解決し、同時に自社の利益も追求できるという新たな経営モデルが提案されたのです。
IT業界におけるCSVの重要性
IT業界でもCSVの考え方は重要です。例えば、デジタルデバイドの解消(情報格差の是正)に取り組みながら、新たな市場を開拓するビジネスや、省エネ技術を駆使したグリーンITの推進などがCSVの好例と言えるでしょう。
ITの力で社会課題を解決しながら、ビジネスとしても成立させることができれば、持続可能な形で社会貢献を続けることができます。
今やIT技術は社会のあらゆる場面で活用されており、IT企業には大きな社会的責任と同時に、CSVを実践する多くのチャンスがあります。ITパスポート試験の受験者としても、このような視点を持っておくことは大切です。
CSVとCSRの違い
CSVを理解するうえで避けて通れないのが、CSRとの違いです。混同されがちなこの二つの概念の違いをはっきりさせておきましょう。
CSRの基本概念
CSRとは「Corporate Social Responsibility」の略で、日本語では「企業の社会的責任」と訳されます。これは企業が利益を追求するだけでなく、環境保護や社会貢献などの責任も果たすべきだという考え方です。
企業活動における環境破壊や人権侵害などの社会的な不利益を減らすことを求める概念で、日本企業では環境保全活動や地域貢献活動、寄付などの形で実践されることが多いでしょう。
CSVとCSRの根本的な違い
CSVとCSRの決定的な違いは、「自社の直接的利益に繋がるかどうか」と「活動内容が自社の事業領域かどうか」です。
CSVは社会課題の解決を通じて企業の経済的価値も同時に創出するもので、それ自体が事業として採算がとれることを目指します。
一方、CSRはそれ自体では直接的な経済的利益を生まず、企業の社会的評価の向上などの間接的な効果を期待するものです。
また、CSVは自社の事業領域と同じ領域で行われ、自社の売上増加に直結するのに対し、CSRは必ずしも自社の事業領域と同じ活動をするとは限りません。
「守りと攻め」の対比
CSRとCSVは「守りと攻め」の対比でとらえられることが多いと言われています。
CSRは企業活動による悪影響を防ぎ、企業の存続基盤を維持する「守り」の側面が強いのに対し、CSVは社会課題の解決を通じて新たな市場を開拓し、企業の成長を促進する「攻め」の側面が強いのです。
しかし、企業の経営強化のためには、CSRとCSV両方の側面から社会への貢献が必要だとされています。つまり、「守り」と「攻め」の両方をバランスよく行うことが重要なのです。
具体例で理解するCSVとCSRの違い
以下の例で、CSVとCSRの違いをより具体的に理解してみましょう。
CSRの例(フェアトレード): 消費者が同じ作物に高い価格を払うことで、貧しい農民の手取り額を増やす。これは価値の再配分であり、直接的な企業利益には繋がりにくい。
CSVの例(持続可能な農業支援): 農業の効率性や品質を高める技術や知識を農家に提供することで、農家の収入向上と企業自身の調達コスト削減や品質向上を同時に実現する。社会価値と経済価値の同時創出を目指している。
CSVの考え方を理解することで、企業の社会貢献と利益追求を対立させずに考えられるようになります。ITパスポート試験でも、この違いを問う問題が出題される可能性があるので、しっかりと理解しておきましょう。
CSVを実現するための3つのアプローチ
マイケル・ポーター教授が提唱したCSVの概念では、社会課題解決と利益の両立のための指針として、3つのアプローチが示されています。これらを理解することで、CSVの実践方法がより具体的にイメージできるようになります。
製品と市場の見直し
1つ目のアプローチは、「製品と市場の見直し」です。
このアプローチでは、自社の製品やサービスの価値を見直し、社会的ニーズを満たせる新しい市場を開拓することを目指します。
例えば、栄養価の高い食品を手頃な価格で提供することで栄養不足の問題を解決しながら新たな市場を開拓したり、省エネ製品を開発して環境問題の解決に貢献しながら環境意識の高い消費者層を取り込んだりする方法などが考えられます。
IT分野では、デジタルデバイド(情報格差)の解消に貢献する低価格のデジタル機器やサービスの提供などが、このアプローチに該当するでしょう。
バリューチェーンの生産性の再定義
2つ目のアプローチは、「バリューチェーンの生産性の再定義」です。
バリューチェーンとは、原材料の調達から製品の製造、配送、販売、アフターサービスまでの一連の価値創造活動のことを指します。
このアプローチでは、生産や流通などの段階で省エネや生産性向上を進め、社会的な負荷を減らしながら生産コスト削減を両立することを目指します。
例えば、製造過程でのエネルギー使用量や廃棄物を削減することで、環境負荷の低減とコスト削減を同時に実現することができます。
IT企業では、クラウドサービスの提供によってユーザー企業のサーバー設置・運用コストとエネルギー消費を削減するなどの取り組みが、このアプローチに当たるでしょう。
地域の産業クラスターの創造
3つ目のアプローチは、「地域の産業クラスターの創造」です。
このアプローチでは、企業が資源の調達先などで生産性向上や従業員教育を進めることで、雇用拡大などを通した地域課題解決と生産コスト削減を両立することを目指します。
例えば、メーカーが原材料の調達先である地域の生産者に技術支援を行い、生産性と品質を向上させることで、地域経済の活性化と自社の調達効率の向上を同時に実現することができます。
IT分野では、新興国にITスキルトレーニングを提供することで、現地の雇用創出に貢献しながら、グローバルな人材プールを確保するといった取り組みがこれに該当します。
CSVの2つの実践タイプ
CSVには「インサイド・アウト型」と「アウトサイド・イン型」の2種類の実践タイプがあります。
インサイド・アウト型CSVは、「自社の事業によって社会に正の効果をもたらす」という、内から外へ影響を与える事業です。例えば、電気自動車の開発・販売によって社会のCO2排出量を削減するような取り組みが該当します。
一方、アウトサイド・イン型CSVは、「社会に正の効果をもたらし、それが自社の利益につながる」という、外から内へ影響を与える事業です。例えば、農家に持続可能な農法をアドバイスすることで、長期にわたって自社に良質な農作物を納めてもらうような取り組みが該当します。
両方のアプローチを組み合わせることで、より効果的なCSV経営が実現できるでしょう。ITパスポート試験では、これらのアプローチの違いや特徴を問う問題も出題される可能性があるので、しっかり理解しておきましょう。
企業事例から学ぶCSV実践
CSVの概念をより具体的に理解するために、実際に取り組んでいる企業の事例を見てみましょう。これにより、どのようにして社会的価値と経済的価値を同時に創出しているのかを学ぶことができます。
キリングループのCSV経営
日本でCSVに注力している代表的な企業の一つとして、キリングループが挙げられます。
キリングループは、特定保健用食品(トクホ)に指定されているコーラや無糖紅茶の販売、グループ内の医薬品企業と共同で研究開発した乳酸菌を使用した製品の販売などを行っています。
これは、健康に配慮した食品という社会ニーズに応えつつ、自社の強みを活かした製品を市場に送り出して収益を上げるという、まさにCSVの理念を実践した例です。
また、ビールの原料であるホップ産地の地域活性化や、ワインの原料となるブドウ農家への技術提供を通した産業の創造、製造工場での節水やリサイクル容器の活用による省資源とコスト削減を進めるなど、先に説明したCSVの3つのアプローチをすべて実践しています。
グローバル企業のCSV事例
世界的に見ても、多くの企業がCSVを実践しています。例えば、以下のような事例があります。
Visa: サービスが行き届いていない人たちに金融サービスを提供し、貧困問題の解決に取り組んでいる。
General Mills: ローカルのフードバンクに食料を提供し、飢餓問題の解決に貢献している。
LEGO: 子どもの遊び、学習、創造のために基金を設立し、教育問題の解決に取り組んでいる。
これらの企業は、それぞれの事業領域と関連した社会課題の解決に取り組むことで、社会的価値と経済的価値の両方を創出しています。
IT業界におけるCSV実践例
IT業界でもCSVの実践例は増えています。
例えば、クラウドサービスを提供する企業が、中小企業のデジタル化を支援することで、中小企業の生産性向上という社会課題の解決に貢献しながら、自社のクラウドサービスの利用拡大という経済的利益を得ているケースがあります。
また、プログラミング教育を提供するIT企業が、若年層のデジタルスキル向上に貢献しながら、将来的な人材確保につなげるという取り組みも、CSVの一例と言えるでしょう。
このように、IT業界ではテクノロジーを活用した社会課題解決と利益追求の両立が可能な分野が多く、CSVの実践が広がっています。
日本における「三方よし」とCSV
CSVと似た考え方として、日本には江戸時代から「三方よし」という商人の心得があります。
「三方よし」とは、「売り手よし」「買い手よし」「世間(社会)よし」の三方が満足するような商売が良い商売だという考え方です。これは、商売を通じて社会にも貢献するという点で、CSVの考え方と通じるものがあります。
日本企業にはこの「三方よし」の考え方が根付いており、CSVの概念を比較的受け入れやすい土壌があると言えるでしょう。
ITパスポート試験では、このような日本独自の経営思想と海外の経営理論の関連性を問う問題も出題される可能性があるので、覚えておくと良いでしょう。
ITパスポート試験における出題ポイント
ITパスポート試験では、経営戦略に関連する分野でCSVが出題されることがあります。具体的にどのような観点から問われるのか、出題ポイントを押さえておきましょう。
試験での位置づけと出題分野
CSVは、ITパスポート試験のストラテジ系(企業と法務・経営戦略・システム戦略)の分野、特に「経営戦略マネジメント」や「ビジネスインダストリ」に関連する項目として出題される可能性があります。
経営戦略に関する概念や理論は、ITパスポート試験において重要な出題分野の一つです。CSVもその一つとして、基本的な概念や他の概念との違いなどが問われることがあります。
想定される出題パターン
ITパスポート試験でCSVが出題される場合、以下のようなパターンが考えられます。
- CSVの基本概念や定義に関する問題
- CSVとCSRの違いを問う問題
- CSVを実現するための3つのアプローチに関する問題
- 具体的な企業事例がCSVのどのアプローチに該当するかを問う問題
- CSVと関連する経営理論や概念(三方よし、サステナビリティ、SDGsなど)との関係を問う問題
これらの問題に対応するには、CSVの基本概念をしっかり理解し、具体的な事例と結びつけて考えられるようになることが大切です。
重要キーワードとその関連性
ITパスポート試験の勉強において、CSVに関連する以下のキーワードも押さえておくと良いでしょう。
- CSV(Creating Shared Value): 共通価値の創造、社会的価値と経済的価値の両立
- CSR(Corporate Social Responsibility): 企業の社会的責任
- 三方よし: 「売り手よし」「買い手よし」「世間よし」の考え方
- ソーシャルビジネス: 社会課題の解決を第一目標に据えたビジネス
- SDGs(Sustainable Development Goals): 持続可能な開発目標
- ESG投資: 環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)に配慮した企業への投資
- サステナビリティ: 持続可能性、環境・社会・経済の調和
これらの概念はCSVと関連が深く、時に比較対象として出題されることもあります。それぞれの違いと関連性を理解しておきましょう。
最新の動向と試験対策
2016年以降、日本でもSDGs推進が始まり、企業による社会課題解決への関心が高まっています。
このような背景から、CSVの概念はビジネス界でますます重視されるようになっており、ITパスポート試験でも出題される可能性が高まっていると言えるでしょう。
試験対策としては、CSVの基本概念と3つのアプローチ、CSRとの違いをしっかり理解し、具体的な企業事例と結びつけて考えられるようになることが大切です。
また、SDGsなど関連する概念との関係性も押さえておくと、より理解が深まります。
CSVはIT技術を活用した社会課題解決とも密接に関わるため、ITパスポート試験においても重要なトピックの一つと言えるでしょう。
まとめと学習のポイント
CSV(共通価値の創造)について、基本概念から実践事例、ITパスポート試験での出題ポイントまで解説してきました。最後に、重要ポイントをまとめて、今後の学習の指針としましょう。
CSV理解のためのポイント整理
CSV(Creating Shared Value)とは、企業が社会的価値と経済的価値の両方を同時に追求する経営手法であり、以下の特徴があります。
- 2011年にマイケル・ポーター教授によって提唱された概念
- 社会課題の解決と企業利益の両立を目指す
- CSRとは異なり、自社の事業領域と直結した形で社会貢献を行う
- 「製品と市場の見直し」「バリューチェーンの生産性の再定義」「地域の産業クラスターの創造」の3つのアプローチがある
- インサイド・アウト型とアウトサイド・イン型の2つの実践タイプがある
- 日本の「三方よし」の考え方と通じるものがある
これらのポイントをしっかりと理解し、具体的な企業事例と結びつけて考えられるようになることが大切です。
ITパスポート試験での効果的な学習法
ITパスポート試験でCSVを学ぶ際の効果的な学習方法をいくつか紹介します。
- 基本概念の理解と暗記: CSVの定義、3つのアプローチ、CSRとの違いなど、基本概念をしっかり理解し、暗記しましょう。
- 具体例との結びつけ: キリングループなどの具体的な企業事例と結びつけて理解することで、記憶に定着しやすくなります。
- 関連概念との比較: CSR、三方よし、ソーシャルビジネス、SDGsなど関連する概念と比較しながら学ぶことで、理解が深まります。
- 最新の動向のチェック: 企業のCSV実践事例や社会課題解決への取り組みなど、最新の動向をチェックすることも大切です。
- 模擬問題の活用: CSVに関する模擬問題を解くことで、試験での出題パターンに慣れましょう。
これらの方法を組み合わせることで、CSVについての理解が深まり、ITパスポート試験での対応力も高まるでしょう。
次に学ぶべき関連用語
CSVを理解したら、次に以下の関連用語についても学んでおくと良いでしょう。
- SDGs(持続可能な開発目標): 2030年までに達成すべき17の国際目標
- ESG投資: 環境・社会・ガバナンスに配慮した企業への投資
- サステナビリティ経営: 環境・社会・経済の調和を目指す経営手法
- イノベーション理論: シュンペーターやクリステンセンなどのイノベーション理論
- コーポレートガバナンス: 企業統治の仕組み
これらの概念はCSVと関連が深く、ITパスポート試験でも出題される可能性があります。CSVの学習を通じて、企業経営と社会の関係性についての理解を深め、試験対策に役立てましょう。
CSVの理解は、ITパスポート試験の合格だけでなく、将来的にビジネスパーソンとして活躍する上でも重要な知識となります。社会課題解決と経済的利益の両立という視点は、今後のビジネス環境においてますます重要になってくるでしょう。
練習問題と解説
最後に、CSV(共通価値の創造)に関する練習問題を通して、理解度をチェックしてみましょう。
練習問題1:CSVの基本概念
問題:CSV(Creating Shared Value)の説明として最も適切なものはどれか。
- 企業の社会的責任を果たすために行う寄付や社会貢献活動のこと
- 社会課題の解決を第一目標に据えた非営利ビジネスのこと
- 企業が社会的価値と経済的価値を同時に創出する経営手法のこと
- 環境、社会、ガバナンスに配慮した企業への投資手法のこと
解答:3
解説: CSVは、企業が社会的価値(社会課題の解決)と経済的価値(利益)を同時に創出する経営手法です。選択肢1はCSR(企業の社会的責任)の説明に近く、選択肢2はソーシャルビジネスの説明、選択肢4はESG投資の説明であり、いずれもCSVとは異なります。
練習問題2:CSVとCSRの違い
問題:CSVとCSRの違いに関する説明として不適切なものはどれか。
- CSVは自社の事業領域に関連した社会課題解決を行うのに対し、CSRは必ずしも自社の事業領域と同じ活動をするとは限らない
- CSVは社会課題解決と利益追求の両立を目指すのに対し、CSRは社会的責任の遂行を主目的とする
- CSVは「攻め」の側面が強いのに対し、CSRは「守り」の側面が強い
- CSVは短期的な社会貢献を目指すのに対し、CSRは長期的な企業価値の向上を目指す
解答:4
解説: 選択肢4が不適切です。実際には、CSVは長期的な視点で社会課題解決と企業価値向上の両立を目指し、CSRも短期的な社会貢献に留まらず、企業の持続可能性に貢献するものです。選択肢1、2、3はCSVとCSRの違いを正しく説明しています。
練習問題3:CSVの3つのアプローチ
問題:あるIT企業が、クラウドサービスの提供により顧客企業のサーバー設置・運用コストとエネルギー消費を削減する取り組みを行っている。このCSV実践は、ポーター教授が提唱した3つのアプローチのうち、どれに最も該当するか。
- 製品と市場の見直し
- バリューチェーンの生産性の再定義
- 地域の産業クラスターの創造
- イノベーションによる競争優位の確立
解答:2
解説: クラウドサービスの提供により顧客企業のコストとエネルギー消費を削減する取り組みは、顧客のバリューチェーン(価値創造活動)の生産性を高めることに貢献しています。これは「バリューチェーンの生産性の再定義」に該当します。選択肢4の「イノベーションによる競争優位の確立」はCSVの3つのアプローチには含まれていません。
練習問題4:CSV実践事例
問題:次のうち、CSVの実践事例として最も適切なものはどれか。
- IT企業が利益の一部を使って地域の清掃活動に参加する
- 食品メーカーが健康に配慮した商品を開発し、生活習慣病の予防に貢献しながら売上を伸ばす
- 企業が年に一度、社員に環境保護団体でのボランティア活動を義務付ける
- 企業が自社のイメージアップのために芸術文化支援を行う
解答:2
解説: 選択肢2の「食品メーカーが健康に配慮した商品を開発し、生活習慣病の予防に貢献しながら売上を伸ばす」が、社会課題(健康問題)の解決と経済的利益(売上向上)を両立させるCSVの実践事例として最も適切です。他の選択肢は、いずれも社会貢献活動ではあるものの、自社の事業活動と直結せず、経済的利益の追求を明確に意図していないため、CSVというよりはCSRに近い活動といえます。
これらの練習問題を通して、CSVの基本概念、CSRとの違い、実践方法などについての理解を深めることができました。ITパスポート試験の際には、このようなCSVの基本的な考え方や事例を押さえておくことが大切です。
CSV(共通価値の創造)は、現代のビジネス環境において重要な概念であり、ITパスポート試験でも押さえておくべきポイントの一つです。この記事を通じて、CSVの基本概念や実践方法、ITパスポート試験での出題ポイントなどを理解していただけたら幸いです。
今後も経営戦略に関する知識を深め、ITパスポート試験合格を目指して頑張りましょう!