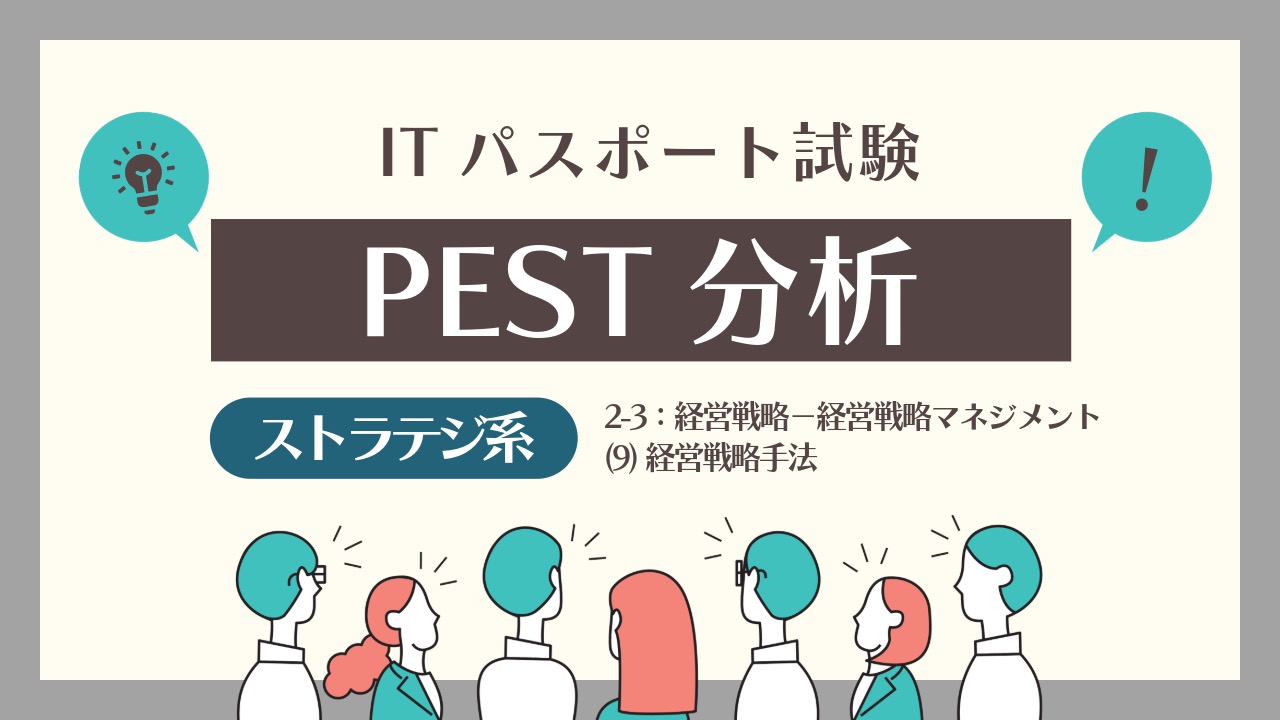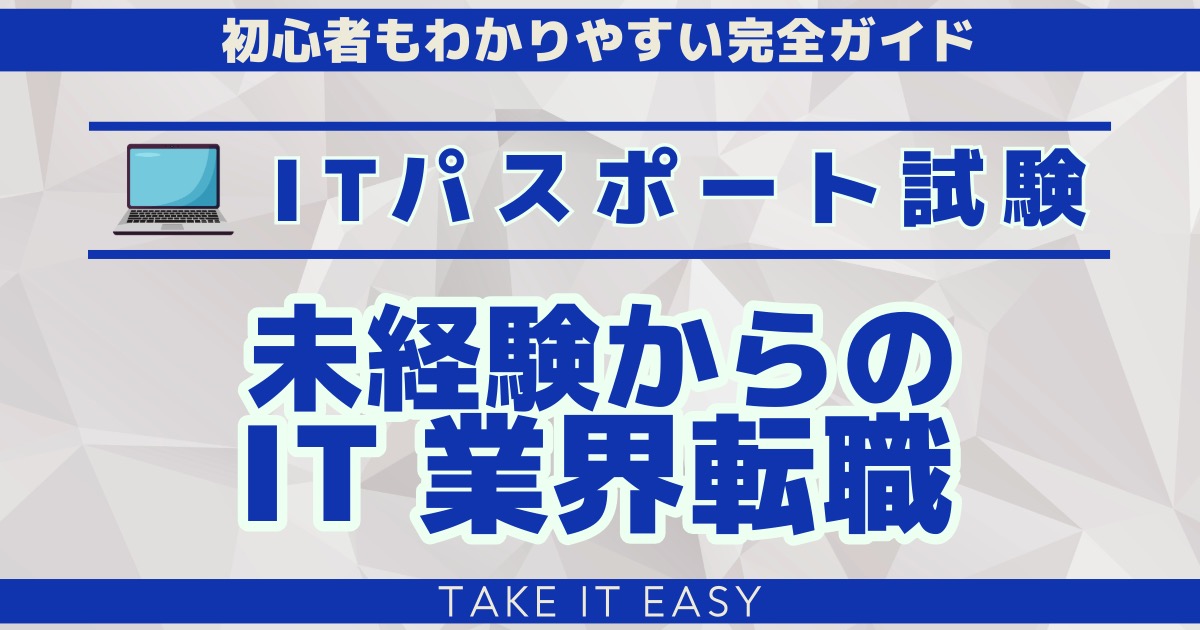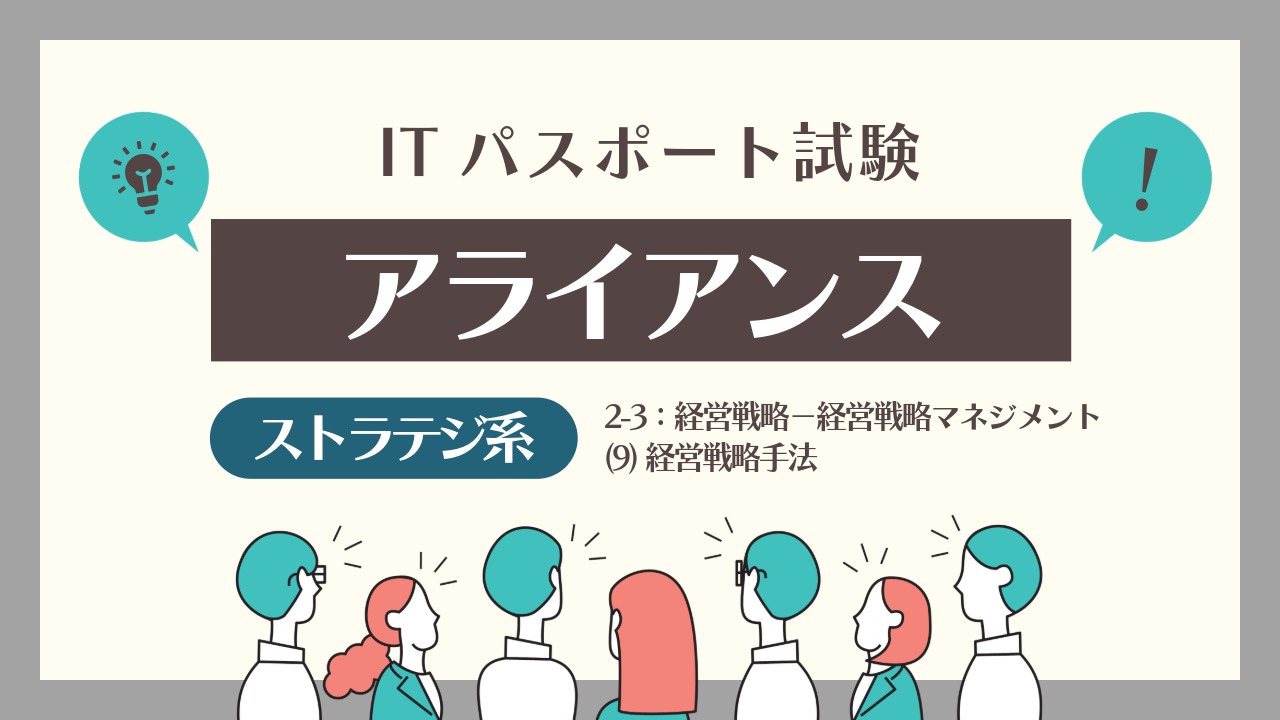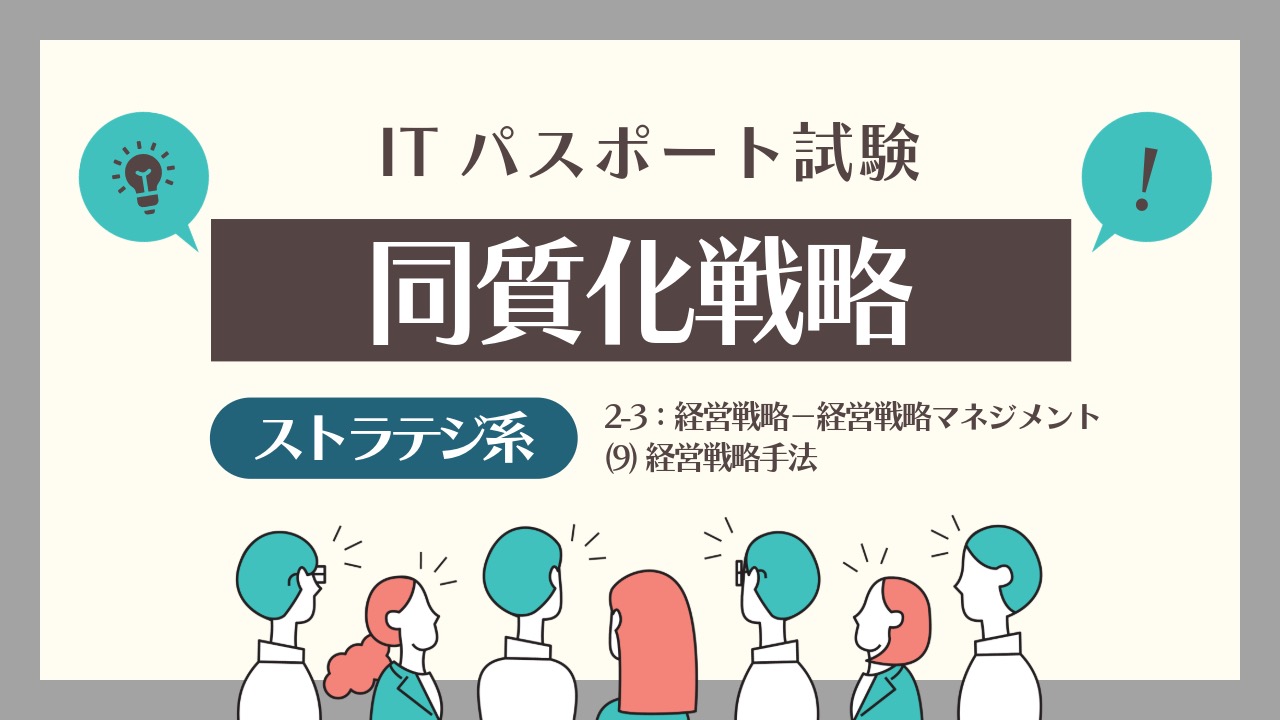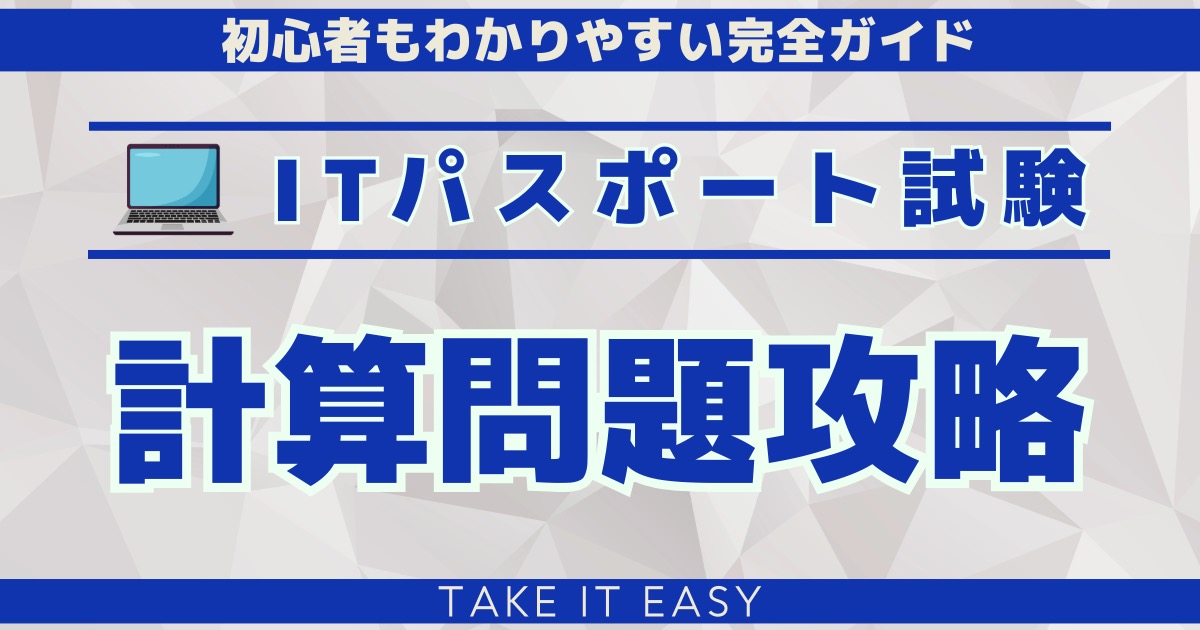ITパスポート試験内容完全ガイド:3つの出題分野を徹底解説!【初心者向け】

ITパスポート試験は、ITに関する基礎知識を証明する国家資格として年々注目度が高まっています。2023年度には26万人を超える受験者を集め、累計では200万人を突破するなど、そのニーズはますます拡大しています。「ITは興味あるけど、何から始めればいいのかわからない」「デジタル時代に必要な知識を体系的に学びたい」という方にとって、最初の一歩として最適な資格です。
本記事では、ITパスポート試験の基本構成から3つの出題分野(ストラテジ系、マネジメント系、テクノロジ系)の詳細まで、初心者の方にもわかりやすく解説します。試験の概要を理解することで、効率的な学習計画が立てられ、合格への道のりがより明確になるでしょう。各分野の特徴や出題傾向を知ることで、「何を」「どのように」学べばよいのかが見えてきます。デジタル社会の基礎教養を身につけるための第一歩を、この記事と共に踏み出してみましょう。
試験の基本情報
ITパスポート試験の基本情報について解説します。この試験がどのような資格なのか、試験の実施方法、合格基準など、受験を検討する際に知っておくべき基本的な情報を紹介します。これらを把握することで、効率的な学習計画を立てることができます。
ITパスポートとは
ITパスポート(略称:iパス)は、経済産業大臣が実施する情報処理技術者試験の一つです。この試験は「情報処理の促進に関する法律」に基づいており、全12区分ある情報処理技術者試験の中で最も基礎的な位置づけとなっています。
2009年に開始されたこの試験は、特にIT専門家だけでなく、一般の社会人や学生も対象としています。「職業人が共通に備えておくべき情報技術に関する基礎的な知識」を証明する資格として、デジタル社会の基礎教養を示すものとなっています。
資格取得のメリットとしては、ITの基礎知識習得だけでなく、経営やビジネスに関する幅広い知識も得られること、就職・転職時の優位性、そしてDX推進の基盤づくりにも役立つことが挙げられます。現代社会ではどのような職種であってもITスキルが必要とされており、その基礎を体系的に学べる点が大きな魅力です。
試験形式と受験方法
ITパスポート試験は、CBT(Computer Based Testing)方式で実施されます。つまり、試験会場に設置されたコンピュータを使用して受験する形式です。紙の試験ではないため、自分のペースで問題に取り組めるというメリットがあります。
試験時間は120分で、四肢択一式(4つの選択肢から1つの正解を選ぶ形式)の問題が全部で100問出題されます。これは一問あたり平均1分12秒しかないことになるので、テンポよく解答する必要があります。
受験方法も非常に柔軟で、全国47都道府県の試験会場で随時実施されているため、自分の都合に合わせて受験日を選ぶことができます。受験料は7,500円(税込)で、特に受験資格はなく、誰でも受験可能です。申し込みはオンラインで行い、受験日の数日前まで予約可能なので、学習の進み具合に合わせて受験日を決められる点も魅力的です。
合格基準と採点方法
ITパスポート試験の合格基準は以下の2つの条件を満たす必要があります:
- 総合評価点:1,000点満点中600点以上(60%以上)
- 各分野別評価点:ストラテジ系、マネジメント系、テクノロジ系のそれぞれについて1,000点満点中300点以上(30%以上)
つまり、総合点が高くても、一つでも分野の得点が300点を下回ると不合格となるということです。これは、ITパスポートが特定の分野に偏らない、バランスの取れた知識を持つことを求めているからです。
採点方法の特徴的な点として、IRT(Item Response Theory:項目応答理論)に基づいて行われることが挙げられます。これは、単純に正答数だけでなく、問題の難易度も考慮した採点方法です。また、出題される100問のうち92問だけが採点対象となり、残りの8問は将来の出題のための評価問題となっています。
合格発表は受験した月の翌月15日前後に行われますので、比較的早く結果を知ることができます。
3大出題分野の概要
ITパスポート試験の出題分野は大きく3つに分かれており、それぞれ「ストラテジ系」「マネジメント系」「テクノロジ系」と呼ばれています。これらの分野が互いにどのような関係にあり、どのような内容が問われるのかを理解することが、試験攻略の第一歩となります。
3つの分野と出題割合
ITパスポート試験の3大分野の出題割合は以下のようになっています:
- ストラテジ系(経営全般):約35問(全体の35%)
- マネジメント系(IT管理):約20問(全体の20%)
- テクノロジ系(IT技術):約45問(全体の45%)
この割合からも分かるように、ITパスポートはIT技術だけでなく、経営戦略や管理に関する知識もバランスよく問われる総合的な試験となっています。
| 分野 | 出題割合 | 主な内容 |
|---|---|---|
| ストラテジ系 | 35% | 企業活動、法務、経営戦略、システム戦略など |
| マネジメント系 | 20% | システム開発、プロジェクト管理、サービス管理など |
| テクノロジ系 | 45% | 基礎理論、ネットワーク、セキュリティ、データベースなど |
テクノロジ系の出題が最も多いものの、ストラテジ系も重視されていることがわかります。この構成は、ITの知識だけでなく、その知識をビジネスにどう活かすかという視点も重要視していることを示しています。
分野間の関連性
ITパスポート試験の3大分野は、それぞれが独立したものではなく、実際のビジネスシーンでは密接に関連しています。例えば、企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)を考える際には、ストラテジ系の経営戦略、マネジメント系のプロジェクト管理、そしてテクノロジ系のクラウドやAIなどの技術知識が総合的に必要となります。
ストラテジ系では「何をするべきか」の計画と方針、マネジメント系では「どのように実行するか」の管理方法、テクノロジ系では「何を使って実現するか」の技術的手段を学びます。実際のビジネスでも、この3つの視点すべてが重要です。
3分野の関連性を理解することで、単なる知識の暗記ではなく、実践的な理解が深まります。これはITパスポート取得後のキャリアにおいても、非常に役立つ考え方です。
効果的な学習アプローチ
ITパスポート試験の合格には、各分野でバランスよく300点以上を取得する必要があるため、偏りのない学習が重要です。初めての方には、以下のような学習アプローチがおすすめです:
- 全体像の把握から始める:まずは3分野すべての基本概念を広く浅く学んで、全体像を掴みましょう。
- 出題頻度の高い分野を重点的に学習する:
- ストラテジ系:法務、ビジネス、企業活動
- マネジメント系:サービス管理、プロジェクト管理、システム監査
- テクノロジ系:セキュリティ、ネットワーク、データベース
- 弱点分野を集中的に強化する:模擬試験などで自分の弱点を見つけ、その分野を重点的に学習しましょう。
- 実践問題で知識を定着させる:単なる暗記ではなく、問題演習を通じて実践的な理解を深めることが大切です。
学習時間の目安としては、ITの基礎知識がない方で約100〜180時間程度と言われています。1日2時間の学習で3ヶ月程度が一般的な学習期間となりますが、IT業界での実務経験や関連知識によって個人差が大きいことを覚えておきましょう。
ストラテジ系の詳細解説
ストラテジ系は、企業活動や経営戦略、法務などに関する基礎知識が問われる分野です。全体の約35%を占め、日常業務では経営やビジネスに関わる内容が中心となります。単なる知識の暗記ではなく、経営的視点からITをどう活用すべきかという応用力も問われます。
企業と法務
企業と法務の分野では、企業活動の基本と、ビジネスに関わる法律知識が問われます。企業活動では、企業の組織構造や形態(階層型組織、機能別組織、職能別組織、マトリックス組織など)、経営管理の基本的な考え方としてのPDCAサイクル、そして財務諸表(貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書)の読み方や分析方法などを学びます。
法務では、知的財産権(著作権法、特許法などの産業財産権関連法規)、情報セキュリティに関わる法律(不正アクセス禁止法、個人情報保護法など)、そして労働に関する法律(労働基準法、労働者派遣法)などが範囲となります。また、ソフトウェアのライセンス形態やコンプライアンス、コーポレートガバナンスといった概念も重要です。
最新の出題傾向によると、法務分野は特に出題頻度が高く(7〜8問程度)、著作権や個人情報保護に関する問題が多く出題されます。実務でもよく遭遇する内容ですので、しっかりと理解しておくことが大切です。
経営戦略
経営戦略の分野は、経営戦略マネジメント、技術戦略マネジメント、ビジネスインダストリの3つの中分類で構成されています。ここでは、企業の経営方針や戦略に関する基本的な概念が問われます。
経営戦略マネジメントでは、SWOT分析(強み・弱み・機会・脅威の分析)やプロダクトポートフォリオマネジメント(PPM)、顧客満足度、CRM(顧客関係管理)、SCM(サプライチェーンマネジメント)などの代表的な経営情報分析手法や経営管理システムについて学びます。
技術戦略マネジメントでは、企業の技術開発戦略の意義や目的について理解します。そして、ビジネスインダストリでは、電子商取引(EC)やPOSシステム、ICカード・RFIDなどの各種ビジネス分野での代表的なシステムの特徴について学びます。
経営戦略分野は5〜6問程度出題される傾向があり、特に経営分析手法やビジネスモデルに関する問題が頻出します。技術の知識だけでなく、ビジネス視点での理解が求められる分野です。
システム戦略
システム戦略の分野は、システム戦略とシステム企画の2つの中分類からなります。企業におけるITの戦略的活用に関する知識が問われます。
システム戦略では、情報システム戦略の意義と目的、戦略目標、業務改善、問題解決などに向けた考え方を学びます。また、クラウドコンピューティング、IoT、ビッグデータなどの最新技術動向に関する知識も問われます。
システム企画では、システム化計画の目的や、現状分析に基づく業務要件定義の目的、IT調達の基本的な流れなどについて理解します。企業がシステムを導入する際のプロセスや考慮すべきポイントについての知識が必要です。
システム戦略分野も5〜6問程度出題される傾向があり、近年ではDX(デジタルトランスフォーメーション)に関する問題や、クラウドサービスの活用に関する問題が増えています。技術の進化に伴い、出題内容も更新されていく分野です。
ストラテジ系の学習ポイント
ストラテジ系を効率的に学習するためのポイントをいくつか紹介します。まず、出題頻度が特に高い法務(7〜8問)、ビジネス(7〜8問)、企業活動(7〜8問)を重点的に学習しましょう。次に多いのがシステム戦略(5〜6問)と経営戦略(5〜6問)です。
専門用語や概念モデルの理解が重要です。例えば、ポーターの競争戦略、SCORモデル、BSC(バランス・スコアカード)などの重要な概念モデルはしっかり理解しておきましょう。難しい経営用語や法律用語も、基本的な意味を押さえておくことが大切です。
ストラテジ系の問題は、単なる知識の暗記ではなく、状況に応じた適切な判断を問うものが多いです。過去問を解きながら、課題分析力と論理的思考力を鍛えることが効果的です。また、普段からビジネスニュースに触れることで、実践的な理解が深まります。
初心者にとっては経営や法律の専門用語が難しく感じるかもしれませんが、基本的な概念を理解し、実例と結びつけて考えることで、徐々に理解が深まっていきます。
マネジメント系の詳細解説
マネジメント系は全体の約20%を占め、主にシステム開発やプロジェクトマネジメント、サービスマネジメントなどに関する基礎知識が問われます。ITを活用する際の「どのように管理するか」という視点が重要な分野で、実務においても役立つ知識が多く含まれています。
システム開発技術とソフトウェア開発管理技術
システム開発技術では、要件定義、システム設計、プログラミング、テスト、ソフトウェア保守などシステム開発のプロセスの基本的な流れを学びます。また、システム開発における見積りの考え方なども含まれます。
具体的には、システム開発の工程(要件定義→設計→製造→テスト→運用)やV字モデルなどの開発モデルについての理解が求められます。各工程での作業内容や成果物についても問われますが、ITパスポートではあくまで基本的な内容に限定されます。
ソフトウェア開発管理技術では、代表的な開発モデルや開発手法に関する意義や目的を学びます。ウォーターフォールモデルやアジャイル開発、スパイラルモデルなどの開発手法の特徴と、どのような場合に適しているかといった知識が問われます。
最近ではアジャイル開発やDevOpsなどの比較的新しい手法についても出題される傾向があります。IT業界の変化に伴い、出題内容も更新されていることに注意しましょう。
プロジェクトマネジメント
プロジェクトマネジメントの分野では、プロジェクト管理の意義、目的、考え方、プロセスなどを学びます。プロジェクトの立ち上げから終了までの一連の流れや、各プロセスでの管理手法についての知識が問われます。
具体的には、プロジェクト憲章の作成、WBS(Work Breakdown Structure)によるタスク分解、スケジュール管理(ガントチャートやPERT図)、コスト管理、品質管理、リスク管理などが含まれます。また、プロジェクトにおけるステークホルダー(利害関係者)の管理方法なども重要な知識です。
プロジェクトマネジメントは4〜6問程度出題される傾向があり、特にスケジュール管理や進捗管理に関する問題が多く見られます。開発現場でよく使用される手法や用語についても理解しておくことが大切です。
ITプロジェクトの成功率は必ずしも高くないことから、効果的なプロジェクト管理の知識は実務でも非常に重要視されています。基本的な概念をしっかり理解しておきましょう。
サービスマネジメントとシステム監査
サービスマネジメントでは、ITサービスマネジメントの意義、目的、考え方などを学びます。また、サービスデスク(ヘルプデスク)の役割や、コンピュータやネットワークなどのシステム環境整備に関する考え方も含まれます。
ITILという国際的なサービス運用の規格に関する基本的な知識も問われます。サービスレベル管理、インシデント管理、問題管理、変更管理、構成管理など、サービス運用に関わる重要なプロセスについて理解しておく必要があります。
システム監査では、システム監査の意義、目的、考え方、対象、計画、調査、報告などシステム監査の流れを学びます。情報システムの目的適合性、有効性、機密性、整合性などを点検・評価する監査に関する基本的な知識が問われます。
サービスマネジメントとシステム監査は合わせて8〜12問程度出題される傾向があり、特にサービスレベル管理やインシデント対応、監査手続きに関する問題が多く見られます。システムの安定運用と品質保証に関わる重要な分野です。
マネジメント系の学習ポイント
マネジメント系を効率的に学習するためのポイントをいくつか紹介します。マネジメント系は特定の中分類に大きく偏ることはなく、まんべんなく出題される傾向にあります。その中でも、サービスマネジメント、プロジェクトマネジメント、システム監査からは若干多めの4〜6問程度が出題される傾向があります。
マネジメント系では、基本概念の理解が特に重要です。プロジェクトマネジメントのプロセスや、ITILなどのサービス運用の国際規格は、体系的に理解する必要があります。用語の暗記だけでなく、それぞれのプロセスがなぜ必要なのか、どのような効果があるのかを理解することが大切です。
マネジメント系は場面設定型の事例問題が多いため、設問文の本質をしっかり捉える力を養うことも重要です。過去問を解きながら、様々な状況での適切な判断方法を学びましょう。
初心者にとっては、プロジェクト管理やサービス運用の専門用語が難しく感じるかもしれませんが、日常生活の例に置き換えて考えることで理解が深まります。例えば、プロジェクト管理は旅行の計画立案と実行にも通じるものがあります。
テクノロジ系の詳細解説
テクノロジ系は全体の約45%を占め、ITの技術的な側面に関する基礎知識が問われる分野です。基礎理論からハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク、セキュリティなど、幅広い分野から出題されます。IT初心者にとっては馴染みのない用語も多いですが、デジタル社会で生きていくための基本的な知識となります。
基礎理論とアルゴリズム
基礎理論では、2進数に関する表現や演算、集合と論理演算、確率と統計の基本的な考え方、数値解析および数値計算などが問われます。また、情報量の単位や情報のデジタル化に関する基本的な考え方、AI技術に関する知識なども含まれます。
例えば、2進数・16進数などの数値表現や、ビット・バイト・キロバイトなどの情報量の単位、AND・OR・NOTなどの論理演算について理解する必要があります。最近ではAIやディープラーニングなどの基本概念についても出題されています。
アルゴリズムでは、データおよびデータ構造、順次・選択・繰り返しといったアルゴリズムの基本構造や代表的なアルゴリズム、アルゴリズムの表現方法に関する理解が問われます。フローチャートの読み方や、簡単なプログラムの処理結果を予測する問題なども出題されます。
基礎理論は4〜8問程度出題される傾向があり、特に2進数の計算や論理演算に関する問題が頻出します。コンピュータの動作原理を理解するための基本となる重要な分野です。
コンピュータシステム
コンピュータシステムの分野では、コンピュータの構成要素、システム構成要素、ソフトウェア、ハードウェアに関する基本的な知識が問われます。
コンピュータ構成要素では、CPUの基本動作やメモリの種類と特徴、キャッシュメモリの役割などを理解します。また、システム構成要素では、サーバ・クライアント型システムやクラウドコンピューティングなどのシステム構成の基本的な考え方を学びます。
ソフトウェアでは、OSの基本機能やミドルウェア、アプリケーションソフトウェアの種類と特徴について理解します。ハードウェアでは、入出力装置の種類や特徴、記憶装置の種類と特徴などについて学びます。
コンピュータシステムに関する分野は合わせて6〜9問程度出題される傾向があり、特にCPUの動作原理やメモリの種類、OSの機能などに関する問題が多く見られます。コンピュータの基本的な仕組みを理解するための重要な知識です。
技術要素(ネットワーク、セキュリティなど)
技術要素の分野には、ヒューマンインタフェース、マルチメディア、データベース、ネットワーク、セキュリティなどが含まれます。特にセキュリティとネットワークは重要な出題分野となっています。
セキュリティでは、情報セキュリティの基本概念(機密性・完全性・可用性)、各種セキュリティ対策(暗号化やウイルス対策など)、セキュリティ管理の方法などを学びます。近年のサイバー攻撃の増加に伴い、特に重要視されている分野です。
ネットワークでは、ネットワークの基本構成やプロトコル(TCP/IPなど)、インターネット技術(DNS、HTTP、FTPなど)について理解します。また、LANやWANの違い、無線LANのセキュリティなども重要なトピックです。
データベースでは、データベースの基本概念、リレーショナルデータベース、SQLの基本的な使い方などについて学びます。データの正規化やトランザクション処理などの概念も重要です。
技術要素の中で特に出題頻度が高いのはセキュリティで、非常に多くの問題が出題されます。次いでネットワーク(4〜8問)、データベース(4〜8問)が多く出題される傾向にあります。
テクノロジ系の学習ポイント
テクノロジ系を効率的に学習するためのポイントをいくつか紹介します。テクノロジ系の中で特に出題頻度が高いのはセキュリティで、次いでネットワーク、データベース、基礎理論が多く出題されます。これらの分野を重点的に学習することが効果的です。
テクノロジ系は用語の暗記だけでなく、概念の理解が重要です。例えば、セキュリティでは単に対策を覚えるだけでなく、なぜその対策が必要なのか、どのような脅威に対応するものなのかを理解することが大切です。
実際の問題では、技術的な知識を応用して状況に適した対応を選ぶ形式が多いため、知識の応用力も求められます。過去問を解きながら、知識の適用力を養いましょう。
IT初心者にとっては専門用語が多く難しく感じるかもしれませんが、日常で使っているスマートフォンやパソコンの機能と結びつけて考えることで理解が深まります。例えば、ネットワークはLINEやメールがどのように届くのか、セキュリティはなぜパスワードが必要なのかなど、身近な例で考えてみましょう。
効果的な学習戦略
ITパスポート試験に合格するためには、効率的な学習戦略が欠かせません。ここでは、学習計画の立て方、分野別の攻略ポイント、おすすめの学習リソースなど、効果的な学習方法について解説します。初心者の方でも無理なく取り組める学習アプローチを紹介します。
効率的な学習計画
ITパスポート試験の効率的な学習計画を立てるためのポイントを紹介します。一般的に、ITの基礎知識がない方で約100〜180時間の学習が必要とされています。1日2時間の学習を続けると、約3ヶ月で合格レベルに達することができるでしょう。
まずは学習期間を決め、逆算してスケジュールを立てましょう。例えば、3ヶ月間の学習計画なら、最初の1ヶ月は全分野の基礎知識を広く浅く学び、次の1ヶ月は苦手分野や重要分野を重点的に学習し、最後の1ヶ月は過去問演習と弱点補強に充てるといった計画が効果的です。
学習の進め方としては、テキストを一通り読んでから問題演習に移るよりも、「テキストの1セクションを読む→関連する問題を解く→間違えた問題を復習する」というサイクルで進める方が知識が定着しやすいです。
また、隙間時間を活用した学習も効果的です。通勤・通学時間やちょっとした待ち時間に、スマホのアプリで用語の確認や簡単な問題を解くことで、日々の学習量を増やすことができます。
継続的な学習のためには、無理のないペースで始めることが大切です。最初から高いハードルを設定するとモチベーションが続かないので、例えば「毎日30分だけは必ず勉強する」など、達成可能な目標から始めましょう。
分野別の攻略ポイント
3つの分野それぞれの攻略ポイントを紹介します。
ストラテジ系のポイント:
- 法務、ビジネス、企業活動が特に出題頻度が高いので重点的に学習
- 経営用語や法律用語の基本的な意味を理解する
- 財務諸表の読み方や経営戦略モデルの基本を押さえる
- 著作権や個人情報保護に関する法律は特に重要
マネジメント系のポイント:
- 全体的にバランスよく出題されるので、偏りなく学習する
- プロジェクト管理のプロセスを体系的に理解する
- ITILなどのサービス運用の国際規格の基本概念を押さえる
- 実務に即した場面設定の問題が多いので、状況判断力を養う
テクノロジ系のポイント:
- セキュリティ、ネットワーク、データベース、基礎理論を重点的に学習
- 2進数計算や論理演算などの基礎は確実に理解する
- セキュリティ対策の種類と特徴を押さえる
- ネットワークの基本構成とプロトコルについて理解する
全体として、単なる用語の暗記ではなく、概念の理解と実践的な問題解決能力を養うことが重要です。過去問を解く際も、「なぜその答えが正解なのか」「他の選択肢はなぜ間違いなのか」を考えることで、理解が深まります。
役立つ学習リソース
ITパスポート試験の学習に役立つリソースをいくつか紹介します。
参考書・問題集:
- 初心者向けの解説が詳しいテキスト
- 分野別の問題集
- 過去問題と解説がまとまった問題集
オンラインリソース:
- ITパスポート試験の公式サイト(IPA)
- 無料の学習サイトや過去問サイト
- YouTube上の解説動画
学習アプリ:
- 隙間時間に学習できるスマホアプリ
- 用語集や単語帳アプリ
学習サービス:
- eラーニングコース
- 通信講座
- 対面講座(社会人向け、学生向け)
自分の学習スタイルや好みに合ったリソースを選ぶことが大切です。また、一つのリソースだけでなく、複数の教材を組み合わせることで、より効果的な学習が可能になります。例えば、基本的な概念はテキストで学び、応用力は問題集で鍛え、苦手分野は動画で理解を深めるといった方法です。
無料の学習リソースもたくさんありますので、まずはそれらを活用して学習を始め、必要に応じて有料の教材や講座を検討するとよいでしょう。
まとめ
ITパスポート試験は、ITに関する基礎知識を証明する国家資格として、その価値が年々高まっています。本記事では、試験の基本情報から3大出題分野の詳細、そして効果的な学習戦略まで包括的に解説しました。
試験の基本情報として、CBT方式で実施される120分・100問の試験であり、ストラテジ系(35%)、マネジメント系(20%)、テクノロジ系(45%)の3分野から出題されることを理解しました。合格するためには総合で600点以上、かつ各分野で300点以上を取得する必要があります。
3大出題分野それぞれの特徴と重要ポイントとして、
- ストラテジ系:企業活動、法務、経営戦略、システム戦略などが含まれ、特に法務、ビジネス、企業活動からの出題が多い
- マネジメント系:システム開発、プロジェクト管理、サービス管理、システム監査などが含まれ、まんべんなく出題される傾向がある
- テクノロジ系:基礎理論、コンピュータシステム、ネットワーク、セキュリティなどが含まれ、特にセキュリティからの出題が非常に多い
効果的な学習戦略としては、3〜4ヶ月程度の計画的な学習と、分野別の攻略ポイントを押さえた学習が重要です。単なる暗記ではなく、概念の理解と実践的な問題解決能力を養うことがカギとなります。
ITパスポート試験は、IT専門家だけでなく、一般のビジネスパーソンや学生にとっても有用な知識を問う試験です。デジタル化が進む現代社会において、ITの基礎知識を体系的に学ぶことの意義は大きく、キャリア形成においても大きなアドバンテージとなるでしょう。
この記事を参考に、ぜひITパスポート試験の学習を始めてみてください。基礎から着実に積み上げていけば、IT初心者の方でも十分に合格可能な試験です。デジタル社会を生きるための基礎教養として、ITパスポートの知識があなたの強い味方となることでしょう。