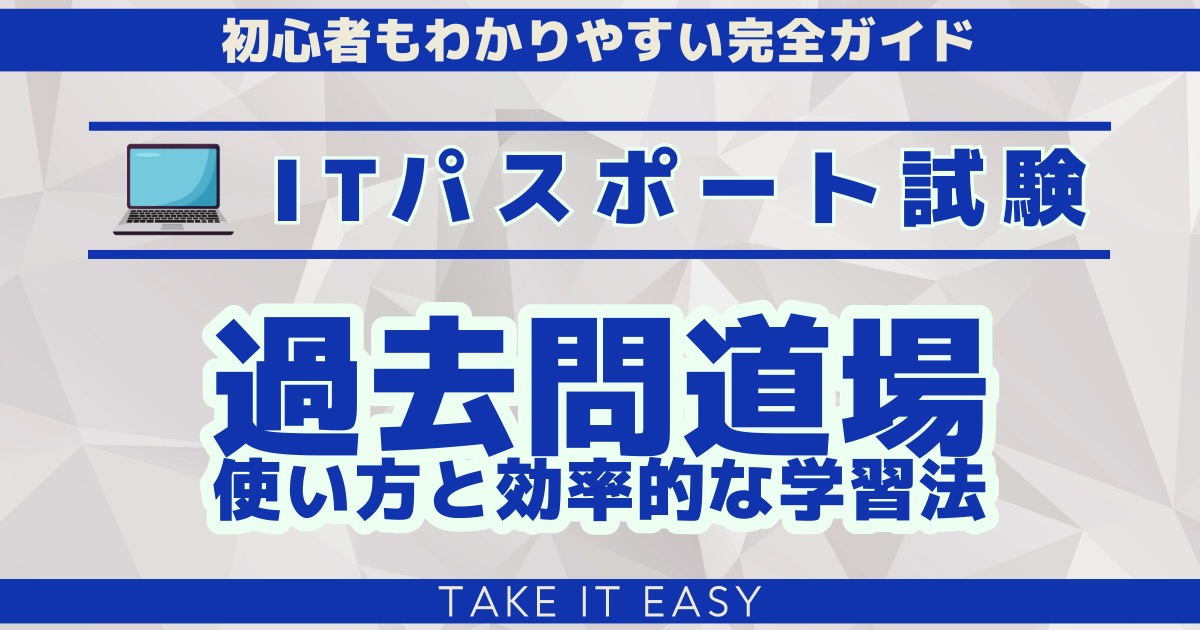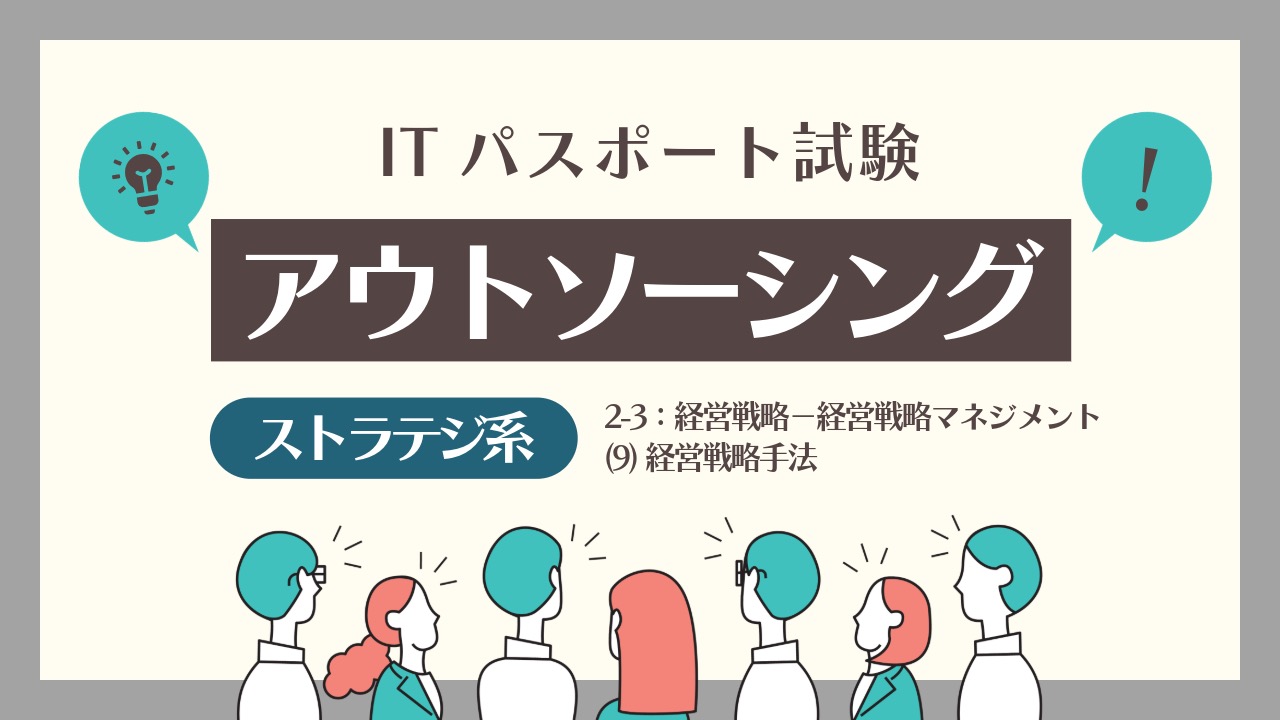ITパスポートの計算問題攻略法【苦手克服のテクニック】
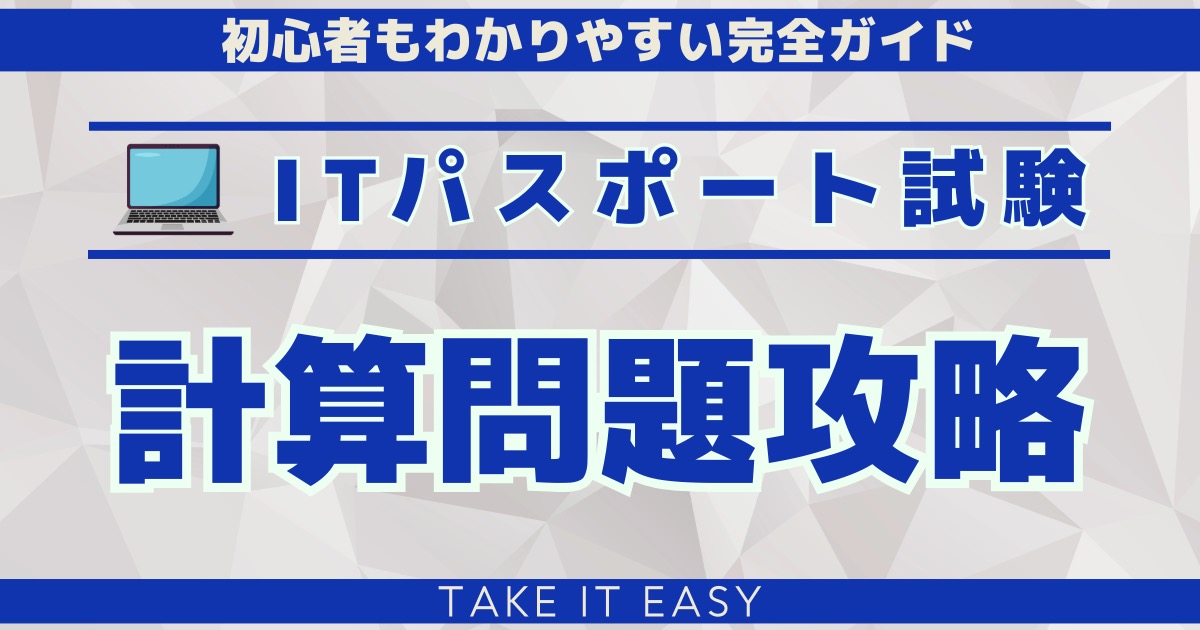
「ITパスポート試験の計算問題が苦手で…」「電卓なしでどうやって解けばいいの?」とお悩みではありませんか?
ITパスポート試験において計算問題は多くの受験者が苦手意識を持つ分野です。しかし、全体の約10%(7〜8問程度)と少ない出題数ながら、攻略法を知れば確実に得点源にできる可能性が高いのが特徴です。
本記事では、ITパスポート試験の計算問題について、「出題傾向」「分野別のパターン」「効率的な解法テクニック」「試験当日の実践戦略」まで徹底解説します。
計算問題は基本的な四則演算で解答できるレベルに設計されており、電卓なしでも十分対応可能です。特に損益分岐点、人日計算、RAID構成などの頻出パターンを理解すれば、確実に得点できるようになります。
この記事を読めば、計算問題への苦手意識を克服し、ITパスポート試験合格に一歩近づくことができるでしょう。計算問題を捨てるのではなく、むしろ得点源にするための具体的なテクニックを身につけていきましょう!
ITパスポートの計算問題とは?
ITパスポート試験における計算問題の全体像を理解することは、効果的な対策の第一歩です。この章では計算問題の出題傾向や試験全体での位置づけについて解説します。
計算問題の出題傾向と重要性
ITパスポート試験における計算問題は、全100問中で約6〜10問程度出題されています。過去の試験データを分析すると、平均して7.8問と全体の1割以下です。
これらの計算問題は、ストラテジ系(経営全般)、マネジメント系(IT管理)、テクノロジ系(IT技術)の全ての分野に出現します。分野別の出題傾向としては、テクノロジ系からの出題が最も多く、次いでストラテジ系、マネジメント系の順となっています。
計算問題の特徴として、基本的な四則演算で解答できるレベルに設計されていることが挙げられます。電卓の持ち込みは禁止されていますが、手計算で十分対応可能な難易度となっています。
また、試験全体において計算問題が占める割合は少ないものの、解法を理解すれば比較的簡単に対応できる問題が多いため、確実な得点源にできる可能性が高いことが重要なポイントです。
計算問題を捨てるべきか?考え方
「計算問題は捨ててもいいのか?」という疑問を持つ方も多いでしょう。結論から言えば、計算問題を完全に捨てることはおすすめできません。
理論的には、計算問題を全て捨てても、残りの問題で72%、各分野で45%程度の正答率があれば合格可能とされています。しかし、ITパスポートは3分野の評価点がそれぞれ300点を下回ると、総合得点が600点以上でも不合格となる特徴があります。
各分野において計算問題が出題されるため、計算問題を完全に無視することは合格への確実な戦略とはいえません。特に、テクノロジ系とストラテジ系では計算問題の出題数が比較的多いため、これらを捨てることで分野別得点が300点を下回るリスクが生じます。
さらに、ITパスポートの計算問題は解法を理解すれば比較的簡単に対応できるものが多く、むしろ確実な得点源にできる可能性が高いことから、計算問題への対策は合格戦略において重要な要素となります。
分野別の計算問題パターンと特徴
ITパスポート試験の計算問題は分野ごとに特徴的なパターンがあります。ここでは各分野の計算問題の特徴と代表的な問題タイプを解説します。
ストラテジ系の計算問題
ストラテジ系では、会計・財務関連の計算問題が頻出です。この分野からは平均して3〜5問の計算問題が出題される傾向があります。
特に多いのが「損益分岐点」に関する計算問題です。例えば、「ある商品を一定の販売価格、変動費、固定費の条件で販売したときの損益分岐点売上高を求める」といった問題が典型的です。
この場合、「損益分岐点売上高=固定費÷(1-変動費率)」「変動費率=変動費÷販売価格」という公式を理解しておくことが重要です。
その他、投資利益率や財務指標(流動比率など)に関する計算問題も出題されることがあります。例えば「流動比率=流動資産÷流動負債×100(%)」といった財務指標の計算も過去問に見られるパターンです。
ストラテジ系の計算問題は基本的な公式を覚えておけば対応できるものが多いため、効率的に得点を重ねることができます。
マネジメント系の計算問題
マネジメント系は3分野の中で計算問題の出題数が最も少なく、平均して1〜2問程度となっています。
マネジメント系で出題される計算問題は、主にプロジェクト管理に関する内容です。特に「人日計算」が重要な頻出パターンとなっています。
例えば、「ソフトウェア開発の仕事に対し、10名が15日間で完了する計画を立てたが、最初の5日間は8名しか確保できない場合、残りの期間で何名の要員が必要か」といった問題が出題されます。
このような問題では、作業量を人数×日数で表す「人日」の概念を理解し、適切に方程式を立てることが求められます。人日計算は「作業量(人日)=人数×日数」という基本概念を把握していれば、応用問題にも対応可能です。
マネジメント系の計算問題は少ないながらも、この分野全体の問題数も少ないため(約20問程度)、確実に得点することが重要です。
テクノロジ系の計算問題
テクノロジ系は計算問題が最も多く出題される分野で、平均して3〜5問程度となっています。
テクノロジ系の計算問題には、いくつかの典型的なパターンがあります:
- RAID構成の容量計算:「容量が500GバイトのHDDを2台使用して、RAID0,RAID1を構成したときの実際に利用可能な記憶容量」を問う問題など。RAID0ではディスク容量が足し算される(500GB×2=1TB)のに対し、RAID1ではミラーリングのため容量は増えない(500GB)という基本的な知識が必要です。
- 基数変換:2進数と10進数の変換や、2進数の計算に関する問題。例えば「2進数10110を10進数に変換した値は?」といった問題が出題されます。
- 稼働率計算:MTBF(平均故障間隔)とMTTR(平均修復時間)を用いて、システムの稼働率を計算する問題。例えば「MTBFが600時間、MTTRが12時間である場合、稼働率はおよそいくらか」といった問題形式です。
テクノロジ系の計算問題も基本的な概念と計算方法を習得することで対応可能です。特に基数変換やRAID構成については、パターンを理解しておくことが重要です。
計算問題を解くための基本戦略
ITパスポート試験の計算問題に効果的に対応するための基本的な戦略について解説します。公式の暗記から手計算のテクニック、問題文の読み解き方まで、基礎となる知識を身につけましょう。
基本公式を確実に覚える
ITパスポート試験の計算問題は、出題パターンがある程度決まっているため、頻出問題の公式を暗記することが最も効果的な対策です。
まず、各分野の重要な公式を確実に覚えましょう:
- ストラテジ系:
- 損益分岐点売上高=固定費÷(1-変動費率)
- 変動費率=変動費÷販売価格
- 流動比率(%)=流動資産÷流動負債×100
- マネジメント系:
- 作業量(人日)=人数×日数
- テクノロジ系:
- 稼働率=MTBF÷(MTBF+MTTR)
- RAIDの容量計算(RAID0は足し算、RAID1は変わらないなど)
これらの公式を確実に覚えておくことで、試験本番でもスムーズに対応することができます。単に公式を暗記するだけでなく、それぞれの意味や適用場面についても理解しておくと、応用問題にも対応しやすくなります。
公式の暗記は、毎日少しずつ繰り返し行うことが効果的です。1日に全ての公式を覚えようとするのではなく、分野ごとに分けて段階的に覚えていくとよいでしょう。
手計算のテクニック
ITパスポート試験では電卓の持ち込みが禁止されているため、すべての計算を手計算(筆算)で行う必要があります。しかし、ITパスポートの計算問題は手計算で解けるレベルに設計されています。
手計算のコツとしては:
- 筆算のスペースを確保する:メモ用紙には十分な余白を取り、計算過程が見やすいように工夫しましょう。
- 概算を活用する:正確な計算ができない場合は、切り上げや切り下げで概算し、選択肢から近い値を選ぶアプローチも有効です。
- 計算の簡略化:例えば割り算で分母が0.8の場合、5/4と変換して計算するなど、計算を簡略化するテクニックを身につけましょう。
- 2進数の計算:2進数の計算では、位取りを意識して桁ごとに計算します。例えば2進数の加算では、各桁ごとに足し算を行い、繰り上がりを処理します。
日頃から電卓に頼らず、手計算の練習を重ねることで、試験当日の対応力を高めることができます。スマホのアプリなどを使う際も、時々は手計算をしてみると良いでしょう。
問題文の読み解き方
計算問題を解く上で重要なのは、問題文を正確に読み解くことです。特に、何を求める問題なのかを明確に理解することが解答の第一歩となります。
問題文の読み解き方のポイント:
- 何を求めているのかを明確にする:「損益分岐点売上高」「必要な要員数」「利用可能な記憶容量」など、求めるべき対象を明確にします。
- 与えられている条件を整理する:問題文から必要な数値や条件を抜き出し、メモに整理します。
- 単位に注意する:特にテクノロジ系では、ビット、バイト、キロバイト、メガバイトなどの単位変換が必要な場合があります。
- 図や表から情報を読み取る:図表が含まれる問題では、そこから必要な情報を正確に読み取ることが重要です。
問題文が長い場合も恐れる必要はなく、むしろ情報が多いほど解法の手がかりが含まれていることが多いため、丁寧に読み解くことが大切です。
最初は時間がかかっても、練習を重ねることで読み解きのスピードが向上します。過去問を使って「問題文を読む→条件を整理する→解法を考える」という流れを繰り返し練習しましょう。
頻出計算問題の解法テクニック
ITパスポート試験によく出題される計算問題のパターンごとに、具体的な解法テクニックを解説します。これらの解法を理解して練習することで、計算問題を得点源に変えることができます。
損益分岐点の計算法
損益分岐点はストラテジ系で最も頻出する計算問題です。損益分岐点とは、売上高と総費用が等しくなる点、つまり利益も損失も発生しない状態のことを指します。
基本公式:
- 損益分岐点売上高 = 固定費 ÷ (1 – 変動費率)
- 変動費率 = 変動費 ÷ 販売価格
具体例: 「ある商品を販売価格300円/個、変動費100円/個、固定費100,000円の条件で販売したときの損益分岐点売上高」を求める問題を解いてみましょう。
- 変動費率を計算: 変動費率 = 変動費 ÷ 販売価格 = 100 ÷ 300 = 1/3 ≈ 0.333…
- 損益分岐点売上高を計算: 損益分岐点売上高 = 固定費 ÷ (1 – 変動費率) = 100,000 ÷ (1 – 1/3) = 100,000 ÷ (2/3) = 100,000 × 3/2 = 150,000円
この計算結果150,000円が答えになります。
損益分岐点の問題では、条件をしっかり整理し、まず変動費率を計算してから損益分岐点売上高を求めるという手順を覚えておくと解きやすくなります。
人日計算のコツ
マネジメント系でよく出題される人日計算は、プロジェクト管理における重要な概念です。人日とは、1人が1日かけて行う作業量の単位です。
基本概念:
- 作業量(人日) = 人数 × 日数
具体例: 「10名が15日間で完了する計画を立てたが、最初の5日間は8名しか確保できない場合、残りの期間で何名の要員が必要か」という問題を解いてみましょう。
- 全体の作業量(人日)を計算: 10名 × 15日 = 150人日
- 最初の5日間の作業量を計算: 8名 × 5日 = 40人日
- 残りの作業量を計算: 150人日 – 40人日 = 110人日
- 残り日数を確認: 15日 – 5日 = 10日
- 必要な要員数を計算: 110人日 ÷ 10日 = 11名
よって、6日目以降に必要な要員数は11名となります。
人日計算の問題では、まず全体の作業量を求め、既に完了した(または予定された)作業量を差し引いて残りの作業量を算出するという手順が基本です。そして、残りの期間で必要な人数や日数を計算します。
RAID構成の容量計算
テクノロジ系でよく出題されるRAID構成の容量計算は、ディスクアレイの基本的な知識が必要です。RAIDはRedundant Array of Independent Disksの略で、複数のディスクを組み合わせて信頼性や性能を向上させる技術です。
主なRAIDレベルと容量計算:
- RAID0(ストライピング): 全ディスクの容量を足し算した値が使用可能容量になる
- RAID1(ミラーリング): 1台分の容量のみが使用可能
- RAID5(パリティ付きストライピング): (ディスク台数 – 1) × 1台あたりの容量が使用可能
具体例: 「容量が500GバイトのHDDを2台使用して、RAID0とRAID1を構成したときの実際に利用可能な記憶容量」を問う問題を解いてみましょう。
- RAID0の場合: 500GB × 2台 = 1,000GB = 1TB (全ディスクの容量を利用可能)
- RAID1の場合: 500GB × 1 = 500GB (ミラーリングのため1台分のみ利用可能)
したがって、RAID0の場合は1TB、RAID1の場合は500GBが答えになります。
RAID構成の問題では、各RAIDレベルの特性(ストライピング、ミラーリング、パリティなど)を理解し、それに応じた容量計算の方法を覚えておくことが重要です。
基数変換のショートカット
テクノロジ系で出題される基数変換は、コンピュータの基礎知識として重要です。特に2進数と10進数の変換がよく出題されます。
2進数から10進数への変換: 2進数の各桁に、右から順に2^0, 2^1, 2^2…の重みをつけて計算します。
具体例: 2進数「10110」を10進数に変換する場合: 1×2^4 + 0×2^3 + 1×2^2 + 1×2^1 + 0×2^0 = 16 + 0 + 4 + 2 + 0 = 22
10進数から2進数への変換: 10進数を2で割り続け、余りを下から順に並べます。
具体例: 10進数「13」を2進数に変換する場合: 13 ÷ 2 = 6 余り 1 6 ÷ 2 = 3 余り 0 3 ÷ 2 = 1 余り 1 1 ÷ 2 = 0 余り 1 よって、「1101」となります。
基数変換の問題では、桁ごとの重みを理解し、順序よく計算することがポイントです。また、計算が複雑な場合は、選択肢を2進数に変換して比較するという逆アプローチも有効です。
稼働率計算の方法
テクノロジ系でよく出題される稼働率計算は、システムの信頼性を評価する指標として重要です。
基本公式:
- 稼働率 = MTBF ÷ (MTBF + MTTR)
- MTBF: Mean Time Between Failures (平均故障間隔)
- MTTR: Mean Time To Repair (平均修理時間)
具体例: 「MTBFが600時間、MTTRが12時間である場合、稼働率はおよそいくらか」という問題を解いてみましょう。
稼働率 = 600 ÷ (600 + 12) = 600 ÷ 612 ≈ 0.98 (約98%)
稼働率の問題では、基本公式を覚えておくことと、分数や小数の計算を正確に行うことがポイントです。また、システムが直列構成や並列構成の場合は、それぞれの稼働率の計算方法が異なりますので注意が必要です。
試験当日の実践テクニック
ITパスポート試験当日に計算問題に効果的に対応するための実践的なテクニックを解説します。限られた時間内で最大限の得点を獲得するための戦略を身につけましょう。
時間配分の方法
ITパスポート試験は120分で100問を解答する形式であり、1問あたりの平均時間は1.2分しかありません。計算問題は一般的に他の問題よりも時間がかかる傾向があるため、効率的な時間配分が重要です。
試験時間の効果的な配分方法:
- 全体の時間配分計画を立てる:
- 計算問題は約8問程度と仮定し、1問あたり2〜3分を目安に、全体で約20分程度を計算問題に充てるよう計画を立てます。
- 残りの約100分を他の92問程度に配分すると、1問あたり約1.1分となります。
- 計算問題の判別と割り切り:
- 問題を見て計算問題だと判断したら、すぐに解けそうか、時間がかかりそうかを瞬時に判断します。
- すぐに解法が思いつかない計算問題は、一旦飛ばして後で戻る戦略を採用します。
- 時間の見える化:
- 例えば30分ごとに何問目まで進んでいるかを確認する目安を決めておきます。
- 60分経過時点で50問前後、90分経過時点で75問前後を目指すなど、ペース配分を意識します。
時間配分の鍵は、すべての問題に均等に時間をかけるのではなく、解ける問題から確実に得点を重ねる戦略を取ることです。特に計算問題については「解ける問題」と「時間をかける必要がある問題」を素早く判断し、適切に時間配分を行うことが重要です。
計算問題への対応順序
計算問題に効率的に対応するためには、問題への取り組み順序を工夫することが効果的です。
計算問題への最適な対応順序:
- 1周目の対応:
- 問題を見て、すぐに解法が分かる簡単な計算問題はその場で解答します。
- 解法が分からない、または時間がかかりそうな計算問題はマークしておき、一旦飛ばします。
- 2周目の対応:
- 全問題に一通り目を通した後、マークしておいた計算問題に戻ります。
- 難易度や自信度に応じて優先順位をつけ、解答していきます。
- 最終確認:
- 残り時間が少なくなったら、未回答の計算問題に対して「消去法」や「勘」も駆使して回答します。
- ITパスポートは減点方式ではないため、空欄よりも何かを選んだ方が良いでしょう。
この対応順序を取ることで、限られた時間内で最大限の得点を獲得する確率が高まります。特に、得意な問題から確実に点数を取り、苦手な問題に時間をかけすぎないという原則が重要です。
概算で選択肢を絞る方法
計算問題では、正確な計算を行わなくても、概算によって選択肢を絞り込むテクニックが有効です。
概算による選択肢絞り込みの方法:
- 桁数での絞り込み:
- 例えば損益分岐点の計算で、結果が「約10万円台」になるはずなのに、選択肢が「1万円台」と「100万円台」しかない場合、計算を簡略化できます。
- 切り上げ・切り下げによる概算:
- 例えば、「498÷0.83」という計算があれば、「500÷0.8=625」と近似できます。
- こうした概算で選択肢を絞り込むことで、計算の手間を省けます。
- 選択肢からの逆算:
- 選択肢が「120」「240」「360」「480」のように明確に異なる場合、正確な計算ではなく、概算で答えの桁数や大きさを推測します。
- 必要に応じて選択肢を元の式に代入し、条件を満たすかどうかを確認する方法も有効です。
- 消去法の活用:
- 明らかに条件に合わない選択肢を消去していき、残った選択肢から最も適切なものを選びます。
概算テクニックは、計算問題に時間をかけすぎないための重要な戦略です。特に選択肢の値に大きな差がある場合は、概算で十分対応できることが多いです。ただし、選択肢が近接している場合は、より正確な計算が必要になることもあります。
効果的な練習方法
ITパスポート試験の計算問題を効果的に攻略するための練習方法について解説します。過去問を使った学習から苦手パターンの克服法まで、実践的なアプローチを紹介します。
過去問を使った練習法
過去問を使った練習は、計算問題対策において最も効果的な方法の一つです。実際の出題パターンと難易度を把握することができ、本番での対応力を高めることができます。
効果的な過去問練習のステップ:
- 過去問の分類と整理:
- 過去数年分の計算問題を集め、「ストラテジ系」「マネジメント系」「テクノロジ系」に分類します。
- さらに各分野内で「損益分岐点」「人日計算」「RAID構成」など、問題タイプごとに整理します。
- 解法プロセスの理解:
- 単に答えを求めるだけでなく、解法のプロセスを理解することを心がけます。
- 各ステップで何をどのように計算しているのかを言語化し、ノートにまとめます。
- 繰り返し練習と時間測定:
- 同じタイプの問題を複数回解くことで、解法のパターンを体得します。
- 計算問題を解く時間を測定し、徐々に解答スピードを上げていきます。
- 誤答分析:
- 間違えた問題は特に重点的に分析し、なぜ間違えたのかを理解します。
- 計算ミス、公式の誤り、問題文の誤読など、誤答の原因を特定します。
過去問演習では、単に多くの問題をこなすよりも、解法の理解と定着に重点を置くことが重要です。特に頻出パターンについては、解法を完全に習得するまで繰り返し練習することをおすすめします。
計算問題特化の学習方法
計算問題にターゲットを絞った学習方法は、効率的な対策につながります。特に苦手意識のある方は、計算問題に特化した学習アプローチを取ることで、短期間で実力を向上させることができます。
計算問題特化の学習ステップ:
- 基本公式のフラッシュカード作成:
- 損益分岐点、人日計算、稼働率計算などの基本公式をフラッシュカードにまとめます。
- 通勤・通学時間などの隙間時間を利用して、繰り返し確認します。
- 計算問題だけを集中的に演習:
- 過去問から計算問題だけを抜き出し、連続して解く練習をします。
- 同じタイプの問題を5問程度連続で解くことで、解法パターンが定着します。
- 手計算の練習:
- スマホやパソコンの電卓を使わず、紙と鉛筆で計算する習慣をつけます。
- 特に分数や小数の計算、2進数の変換などを集中的に練習します。
- 解説動画や専門教材の活用:
- 計算問題に特化した解説動画や参考書を活用し、異なる視点からの説明を理解します。
- 特にビジュアル的な解説は、理解が深まりやすいでしょう。
計算問題特化の学習は、短期間で集中的に行うことで効果を発揮します。例えば、試験の1ヶ月前に1週間程度、計算問題だけに集中して取り組むというアプローチも有効です。
苦手パターンの克服法
計算問題の中でも特に苦手なパターンがある場合、それを集中的に克服することで全体の得点力が向上します。
苦手パターン克服のステップ:
- 苦手パターンの特定:
- 演習を通じて、特に時間がかかる問題や正答率が低い問題タイプを特定します。
- 例えば「2進数の計算」「損益分岐点」など、具体的な問題タイプを把握します。
- つまずきポイントの分析:
- なぜその問題タイプが苦手なのかを分析します。
- 「公式が覚えられない」「計算が合わない」「問題文の理解が難しい」など、具体的な原因を特定します。
- スモールステップでの学習:
- 苦手パターンを細分化し、小さなステップに分けて学習します。
- 例えば2進数の計算が苦手なら、まず2の累乗(1,2,4,8,16…)を覚え、次に簡単な変換から始めます。
- 視覚化と言語化:
- 苦手な概念を図や表で視覚化したり、自分の言葉で説明したりすることで理解を深めます。
- 例えば、RAIDの仕組みを図で描いてみる、損益分岐点の概念を自分の言葉で説明してみるなどです。
- 反復練習と成功体験の蓄積:
- 苦手パターンの問題を集中的に、繰り返し解きます。
- 最初は簡単な問題から始め、徐々に難易度を上げていくことで、成功体験を積み重ねます。
苦手パターンの克服には、「回避する」のではなく「向き合う」姿勢が重要です。特に計算問題は解法が明確なため、適切なアプローチで必ず克服できます。苦手意識を払拭し、むしろ得意分野に変えていく気持ちで取り組みましょう。
まとめ:計算問題攻略のポイント
ITパスポート試験の計算問題攻略について、これまでの内容を総括します。計算問題を得点源に変えるための核心ポイントをまとめました。
計算問題の重要性を再認識
ITパスポート試験における計算問題は全体の約10%(7〜8問程度)を占めており、決して無視できない存在です。解法を理解すれば確実に得点できる問題が多いため、むしろ得点源として活用すべきでしょう。
特に各分野の合格ラインが300点以上と設定されていることを考えると、計算問題を捨てることでリスクが生じる可能性があります。テクノロジ系とストラテジ系は計算問題の出題が比較的多いため、これらの分野での計算問題対策は重要です。
分野別の頻出パターンを把握
計算問題を効率的に攻略するためには、分野別の頻出パターンを把握することが重要です:
- ストラテジ系:損益分岐点計算、財務指標計算
- マネジメント系:人日計算、工数管理
- テクノロジ系:RAID構成の容量計算、基数変換、稼働率計算
これらのパターンは過去の試験で繰り返し出題されているため、集中的に対策することで効率よく得点力を高めることができます。
基本公式と解法の習得
計算問題の攻略には、基本公式と解法パターンの習得が不可欠です。特に以下の公式は必ず覚えておきましょう:
- 損益分岐点売上高=固定費÷(1-変動費率)
- 作業量(人日)=人数×日数
- 稼働率=MTBF÷(MTBF+MTTR)
これらの公式を理解し、適用できるようになれば、多くの計算問題に対応できるようになります。
試験当日の実践戦略
試験当日は以下の戦略を実践しましょう:
- 効率的な時間配分:計算問題に全体の約20分程度を割り当て、残りの時間で他の問題に取り組みます。
- 優先順位の設定:すぐに解ける問題を先に解き、時間のかかる問題は後回しにする戦略を取ります。
- 概算テクニックの活用:正確な計算にこだわりすぎず、概算で選択肢を絞り込む方法も積極的に活用します。
- 全問解答:ITパスポート試験には減点方式がないため、時間が足りなくなった場合でも、すべての問題に回答することを心がけます。
継続的な練習の重要性
計算問題の攻略には継続的な練習が欠かせません。過去問を使った演習、苦手パターンの集中対策、手計算の習慣化などを通じて、計算問題への対応力を高めていきましょう。
特に、解いた問題の解法プロセスを理解し、同じミスを繰り返さないように努めることが重要です。
最後に
ITパスポート試験の計算問題は、「苦手」から「得意」に変えられる可能性が高い分野です。解法パターンが限られているため、適切な対策を講じれば、短期間で実力を向上させることができます。
この記事で紹介した攻略法を実践し、計算問題を確実な得点源にして、ITパスポート試験合格を目指しましょう!


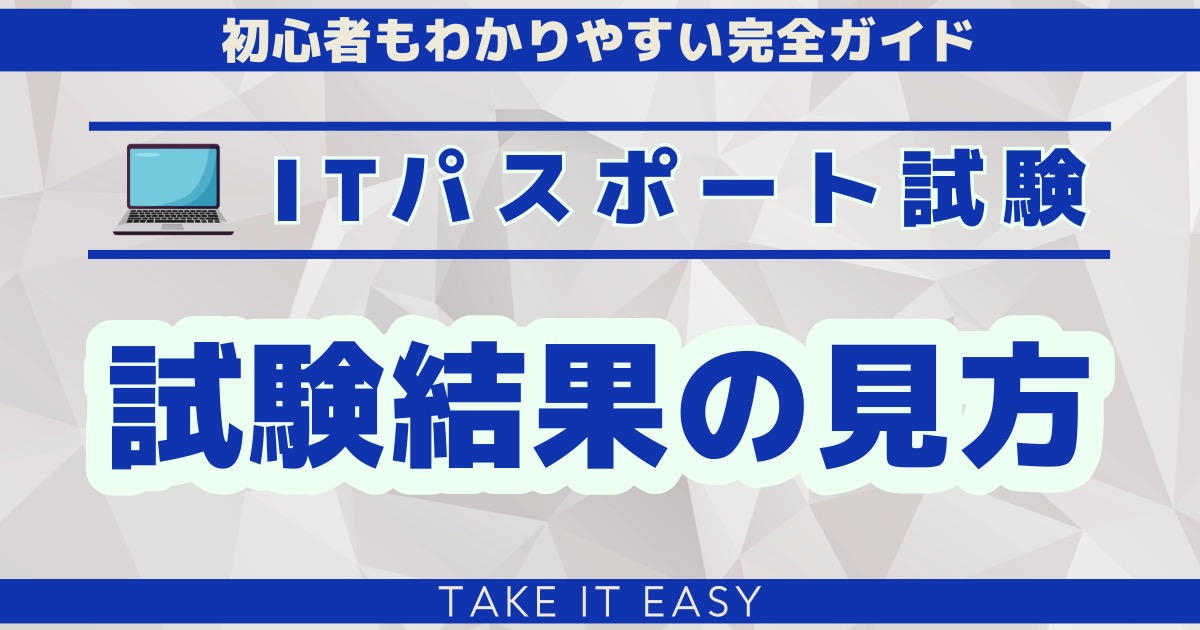
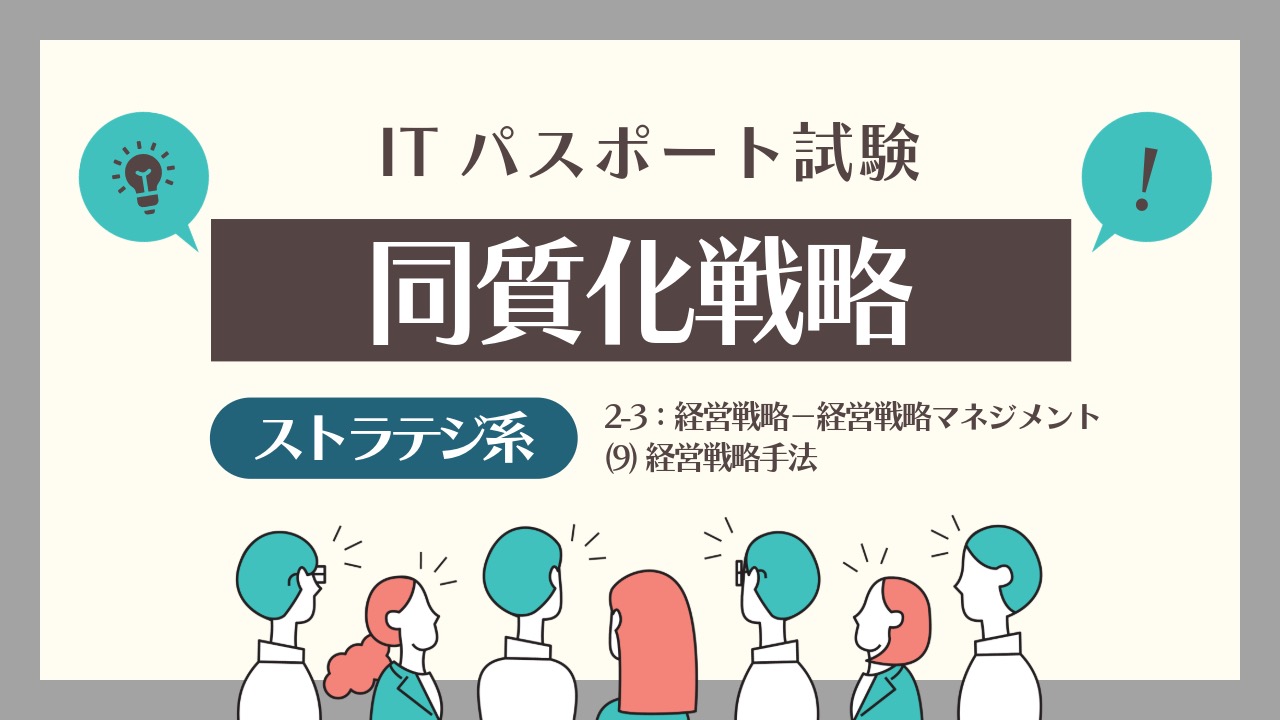
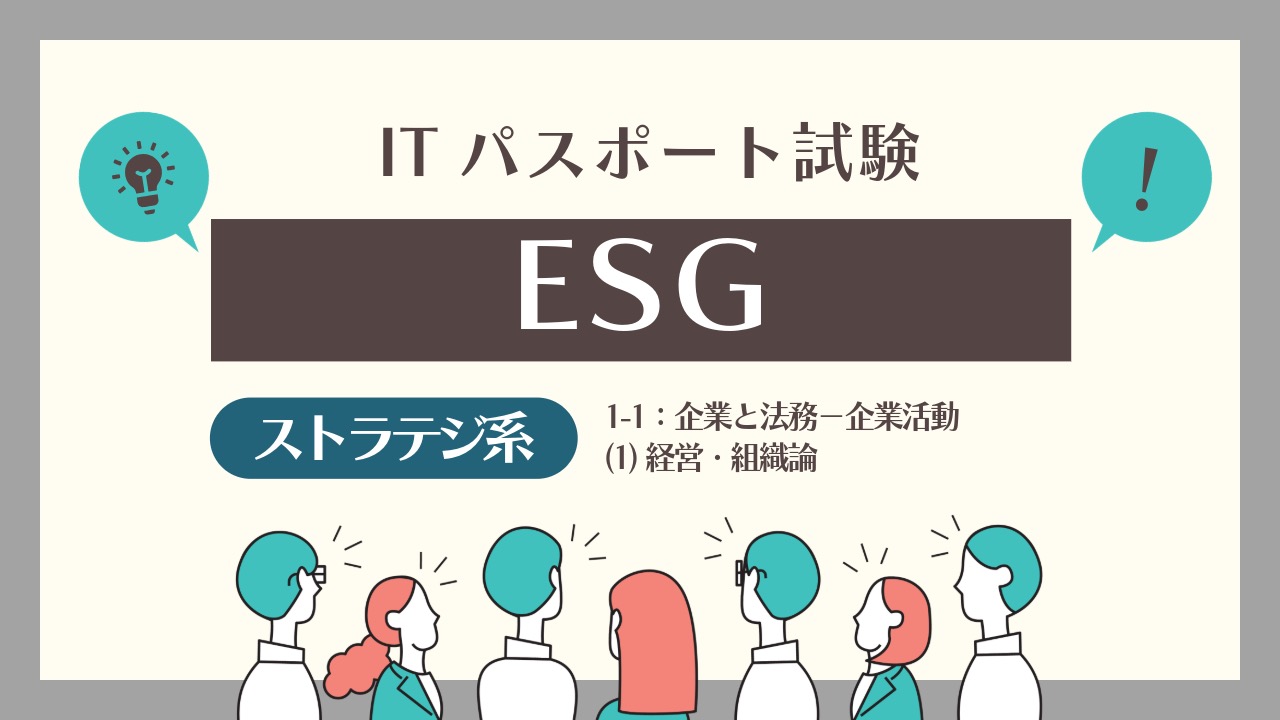
.jpeg)